�u�I�����C���E�I�s�j�I���v
�u�J�W�m�����{��ʖڂɂ���v
�u���{�ɂ͂Ȃ��N�w�v
�u�݂�E�����E�͂Ȃ��v
�u�����ɔ��v
�u�l�ԁA��������Ɓv
�u�n�C�u���b�h�Ɖu�v
�u5�ނ̉ۑ�v
�u�̏��40�N�v
�u��{����̎莆�v
�u���ɓ����x
2321.�J�W�m�����{��ʖڂɂ���@4/27
�ېV�����i�A�Ƃ��낪�ېV�̓J�W�m�𐄐i�B
�����ăJ�W�m�����{��ʖڂɂ���B
�x�T�w�D���́A���s���������������A
�䂫���Ƃ���ł�����B
�g������Ȃ��x�T�w�A�����̐H���ɍ���n���w�B
�Ԃ͋����o�b����������Ȃ������ی쐢�сB
�n�R�l�͔���H���ƌ������r�c���l�B
�ł��D���ŕn�R���Ă����ł͂Ȃ��B
�����ɂ͊������Ƃ����A�l�ł͉z�����Ȃ�
�����ǂ�����B������n�R�l�͈ꐶ�n�R�̂܂܁B
�`���b�gGTP�̂b�d�n�Ǝ��ʉ�B
����̓J�W�m�U�v�iIR)�̍\�}�Ɏ��Ă���B
�č����{��`�̓��{�N�U�̂�����̌`�B
�������{�̊������A�Ŏx����ƂȂ�ƁA
��k�ōςޘb�ł͂Ȃ��B
�����̓V���́A�����̒n�����B
�����͕n�x�̊i���ɂ͉��̊S���Ȃ��B
�������͂ɂ��������͂Ȃ��B
�������������Ɉˑ����A
�D���ɐU���킹�Ă��������}������
���Ɏn�܂�����ł͂Ȃ��B
���ƂȂ����`�ŁA�ێ琭���A����
�����}�����Ƃ��Ă��������ɁA
�����̕��s�̐ӔC��₤�̂͗e�Ղ����A
����͎����}�̐ӔC����ł�����B
����ȑO�ɁA�����ɑI�������Ȃ����ƁA
����������A��}���s�݂ł��邱�Ƃ��A
���{�ɂ͖����`�����݂��Ȃ����Ƃ�
�������͂�����Ǝ����Ă���B
����̑O�����̓T���f�[�����i5.7�j�A�q���Y�̐���A�����_����B
�u�ېV�A���i�͂������ǁA���F�J�W�m�����{���_���ɂ��邼�v
�J�W�m�Ȃ���̂����߂Č����̂́A����1980�N��O���̍��B�����L�Ҏ���A�����̈��{�W���Y�O���ɓ��s�A�S�l���哝�̂Ƃ̓��؉�k����ނ��邽�߃\�E���ɍs�������ł���B�h�������z�e���̍ŏ�K�ɃJ�W�m������A�O���Ȃ̐E���ɗU��ꋰ�鋰��`���Ă݂���c�B�ՌÉG�����Ă����B
��������u���{�ɂ��J�W�m����������o�ό��ʂ����҂ł���I�v�Ƃ̈ӌ������������A�O���l�ό��q�Ŋ؍��J�W�m�͂������I�Ƃ̘b�́u�����ƌ���Ƃ͑�Ⴂ�v�������B
�������݂��A�؍���1�J��������ɐ����Ă���J�W�m�����݂���B
�]���i�J���E�H���j�����h�ɂ� �S���t��A�X�L�[��A�W����A��c��Ȃǂ������Ă��āA���{���{�����ڎw���Ă���IR�i�����^���]�[�g�j�̂���{�̂悤�ȏꏊ�B7 000�l���e�̃J�W�m������B���́A�����������؍��ŗB��A�����������邱�Ƃ��ł���J�W�m�Ȃ̂��B
���̊X�ɍs���A�ُ�Ȍ��i�ɑ�������B�X�ɂ͎���������ł���B�l�X�͏���Ă����Ԃ⎞�v�����ɓ���ēq�����Ɋ����A���h�ɔ��܂荞��ŘA���A�J�W�m�ɒʂ��B�����̊O���l���s�҂Ȃ�Ă��Ȃ��B
���łƂ������̂́u�����v�������ׂ���̂�����A�l�X�͂����u�������v�ɂȂ�B�ƒ����A�j�Y�A���E�E�c�B�J�W�m�n���ł���B
���̂�����́A���ĒY�z�̒��B 90�N��̔p�z�Œǂ��l�߂��A�n��Đ��헪�Ƃ��ăJ�W�m�U�v�����߂��̂����A�ǂ���炱�̌v��͗��ڂɏo�Ă��܂����悤�Ɍ�����B
���āA����n���I�̑O����ŁA ���ېV�̉���{�m���Ƒ��s���̃_�v���I���Ɉ����B�u���̋@�v�����A���{�́u�ېV�v�����i���Ă����u���E���F�n����蕡���ό��{��搮���v��v�Ȃ���̂�F�肵���B���ɃJ�W�m�����܂��̂��B
�͂����茾�킹�Ă��炤���A���{�ɃJ�W�m�͕K�v�͂Ȃ��B���n�A���ցA�����A�I�[�g�A����Ƀp�`���R�܂ł�����{�͂��Ƃ��Ɓu���E�ň��̃M�����v���ˑ��Ǒ卑�v�B���J�Ȍ����ǂ̐���Ŗ�320���l���u���ŕa�v�ɂȂ��Ă���B
����Ȓ��ŁA�Ȃ��J�W�m���K�v�Ȃ̂��H
���{�W�O���͓������A�����͂Ƀg�����v���������܂ꂽ���A �E���\���~�̃S���t�p�i����y�Y�ɁA�j���[���[�N�̋����s����K�˂��̂����A���̎��g�����v�哝�̂́u�J�W�m�̋K���ɘa���K�v���v�ƁD�e�f���z�e�f���q���B�g�����v���͌��X�J�W�m�̌o�c�ҁB�g�����v�ɂ��A�g�����v�̂��߂̃J�W�m���@���H�������B
��Âɍl���Ă���I�킴�킴���{�ɃJ�W�m�����ɗ���O���l�͂��Ȃ��i�J�W�m�͖�140�J���Őݒu����Ă���j�B�ƂȂ�A���F�J�W�m�́u�����������p���锎�ŏ�v�ɂȂ邾�낤�B
����ł����̂��H
�R�����g�F���_�܂��҂�ł���B�����Ȃ班�Ȃ��Ƃ������g���B���R���݂̓q�����ȂǁA�����Ă������Ă��A�����Ƃ��ʔ����Ȃ��B�����X�q�̑�ł����Ȃ��A�n�}�R�[�Ȃ�ʂ�������Ȃ����B
�֘A�L���F�ېV�����i�͊ԈႢ�B�ǂ������̎M�ɂȂ邩�̖��B
https://news.yahoo.co.jp/articles/94536574883078e7da32dcaca7424eb453ead41c
�֘A�L���F�ېV���������A�����E�J�W�m�p�n�̃J�l�Ɖ����B
https://news.yahoo.co.jp/articles/1d29f655de21a616cdb14b1a10a04d999ad244fb
������{�A�����T���f�[�����́A�݂�Ȃ̃E�F���r�[�C���O�A�O�엲�i����
�u�����}�e���A���Y���͍K�����H�v
�́A�}�h���i�́u�}�e���A���E �K�[���v�Ƃ����̂�����܂����B1984�N�����ł�����A������ 40�N�߂����O�̉̂ł��ˁB�}�e���A���E�K�[���Ƃ́A��₨�����D���ȏ����Ƃ����Ӗ��ł��B
�S���w�̐��E�ɂ��A������`�i�}�e���A���Y��)�Ƃ������t������܂��B���b�Z���E W�E�y���N�ɂ��ƁA������`�Ƃ́A����҂������I�ȏ��L�����d�����邱�Ƃł��B������`���ł��������x���ł́A���L�����l�̐����̒��S�I�Ȉʒu���߁A�����ƕs���̍ő�̗v���ɂȂ肤��ƁA�x���N�͏q�Ă��܂��B
�F����́A������`�I�ł��傤���H�����ł͂Ȃ��ł��傤���H ���₨�����~�����Ƃ����̂͐l�ތŗL�̗~���Ȃ̂ŁA���������Ȃ��Ɗ�����������邩������܂���B�������A������`�́A�l��20���N�̗��j�̒��ł͋ɂ߂čŋߏo�Ă����T�O�ł��B���m�Ō���^�̍K���Nj��p�^�[���Ƃ��Ắu����v�����߂ďo�������̂́D15-16���I�̃��[���b�p�A18���I�̃C�M���X�A19���I�̃t�����X�A19-20���I�̃A�����J�����肾�낤�ƌ����Ă��܂��B�܂�A������`�Ƃ́A�������S�N���炢�̊Ԃɏo�Ă����T�O�Ȃ̂ł��B
������`�Ɛ��i�����̊W�ɂ��Ă̌����̌��ʁA������`�I�X���������O���[�v�ł͐_�o�njX�����������Ƃ��m���Ă��܂��B�܂��A������`�͎Ⴂ�l�قNj����X��������Ƃ����������ʂ�����܂��B����ɁA������`�͊e��E�F���s�[�C���O�w�W�ƕ��̑��֊W�����邱�Ƃ��m���Ă��܂��B�܂�A������`�I�Ȑl�́A�K���ł͂Ȃ��X��������Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�������낢��ȂƂ���ŏq�ׂĂ����A�n�ʍ��i�n�ʂƂ��đ��l�Ɣ�r�ł�����B���A���m�A�n�ʁj�Ƃ��߂��T�O�ł��ˁB�n�ʍ��ɂ��K���͒��������Ȃ����Ƃ��킩���Ă��܂��̂ŁA��͂�A������`�I���Ƃ��܂�K���ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�ł��B
����Ȃ̂ɁA�}�h���i�́u�}�e���A���E�K�[���v�����s������A���̃��f���ł������ƌ�����}�������E�������[�̉f��u�a�m�� ���������D���v(1953�N�j�ȂǁA������`�I�Ȑl�Ԋς͌J��Ԃ��b��ɂȂ�܂��B�Ȃ��Ȃ̂ł��傤���H
�ЂƂɂ́A�u���K�I�E���I�Ȍ��R��Ԃ͕s�K�ł���v�Ƃ����������ʂ�����̂ŁA���̋t�����藧�悤�Ɏv���邩�炩������܂���B�����Ƃ��Ă��u�n������E�o������K���ɂȂ����̂ŁA����ɂ��������ɂȂ�ƍK���Ȃ͂��v�ƍl����ꂻ���ɂ��v���܂��B�������A�l�Ԃ̐S�͔���`�ł��B���K�I�E���I�Ȍ��R��Ԃ͕s�K�ł����A���K�I�E���I�ɖ�������Ă� ���قǍK���ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B �w���^�̏�������̌��^�̏���̕����K���x�͍��܂�Ƃ����������ʂ�����܂��B������`�Ɋׂ肷�����A���낢��ȑ̌����y���݂܂��傤�I
�R�����g�F����������`�ł��B���m�Ɉ͂܂�Ă��Ȃ��ƕs���ł��B�_�o�ǓI�X��������܂��B�����A�����K���ł͂Ȃ����Ƃ��܂������ł��B
2322.���{�ɂ͂Ȃ��N�w�@4/29
���̂܂Ƃ߃T�C�g�́A���f�B�A�ł͂Ȃ��A
��ǎ҂ɂ��A���̏Љ�ł���A
�����ɑf�l�̊��z��t�����������́B
����ȏ�̂��̂ł͂Ȃ��B
�{���Ȃ�A�X�̏��̈Ӗ��𗝉����A
������\�����A�ǎ҂ɓI�m�ȃA�h�o�C�X��
����ׂ����B
�������c�O�Ȃ���A�����ɂ́A
�����Ȃ���I�Ȓm�����A
���x�ȕ��͔\�͂��Ȃ����Ƃ́A
�������g����ԗǂ����m���Ă���B
���Ă̏�i�i�e�Ђ̖����j�́A
�����̂悤���ƌ������B
�Ȃ�ΐ��U�ꏑ�����т������B
�����ď����ɏo���鎖�́A
���̕s����A���s�s�ɁA
�^��������邱�Ƃ����Ȃ��B
����̑O�����́A�����V���i4.27�j�̘_�d���]�ł��B
�u���ɋc�_�����ɁA�����Ɛ��E�Ȃ����G���v�F��d�K����
�킽�����ŏ��Ɂu�@�d���āv���ӎ������̂́A�Љ�w�҂̌��c�@������V���ŏ��������]���܂Ƃ߂��{��ǂƂ��������B���c�́u�_�d�v�Ȃ���̗̂֊s�������ɂ����Ȃ��ċv�����A������u�_�d�G���v������ǂ�ł��A�u�v�z�̌��݁v�𑨂��邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ��������Ă����B���ہA���c�͕��w�⌻��v�z���������_�܂ł����R�ɍs�������ċc�_��W�J���Ă����B���ꂩ��40�N�߂��������A���l�Ȍ����̓l�b�g��Ԃɂ����Ă���B�킽�����������|������̍^���ɗ����������A���ɋc�_���Ă������߂̏�����߂������B�����āA���c�̌��t�����Ȃ�A�����Ɛ��E���Ȃ��u�ЂƂ����̊��G�v���������B���̂��߂ɂ��̎��]���n�߂�B����ɘ_�������̂́A���{�Ɛ��E�̊W�ł���B���V�A�̃E�N���C�i�N�U�ƕĒ��Η��ɂ��s���艻���鐢�E�ɂ����āA���{�͎���������Ɉʒu�Â��A�����̈��S���ǂ���邩�B���R�Ɩ����`�A�����Ė@�̎x�z����邽�߂ɁA�������ɂȂ肪���ȕč����x���A���E�̒����ɍv�����ׂ��ł��邱�ƂɈ٘_�͂Ȃ��B���͂�����������铹�ł���B
�Ⴆ�A��N���A���{�͈��S�ۏ� 3�������t�c���肵���B���̂����̍��ƈ��S�ۏ�헪�ł́A���{�̖h�q�s�������Ӎ�����\�����₷������u�\���\���v�����߂邱�ƂŁA���肵�����ۊ����\�z�ł���Ƃ��Ă���B�Ƃ��낪���ې����w�҂̐Γc�~�́u���E�v�ŁA�����\�͂ۗ̕L���܂ލ���̖h�q�͋������A�{���ɗ\���\�������߂�̂��Ƃ����^�����Ă���B�ǂ̎��_�ŕ��͍U���̒��肪�������ƌ��邩�A���{�́u������@���ԁv�̊�͉����B�����ɗ�O������B�������c��A�ނ���\���\���͒ቺ���A�R�g�������������˂Ȃ��B�\���\���̕]�����߂����ẮA���˂����c�_���K�v�ɂȂ낤�B
�O��?���S�ۏ�ɂ��āA���{�ɂǂꂾ���̑I����������̂��B�A�W�A���ې����j����Ƃ���{��呠����͂�u���E�v�Œ��ڂ��ׂ��c�_��W�J���Ă���B�ߔN�̓��{�ɂ́A���{�W�O�A���c�N�v�A���R�R�I�v�ɑ�\�����O�̘H�����������B����̕ČR���V�Ԋ�n�́u�Œ�ł����O�v�����������R�̘H���́A ����}�����̊����ɂ��ׂ����B�䓪�����������Ƃ̑Θb�Ƌ����������������c�̘H�����A�����Ԃْ̋��̍��܂�ɂ���ނ����B���ʂƂ��� �����ւ̑R���f������{�̘H���������c�������A�O��_�c�́u���m�g�[���i�P�F�j���v���Ă���B����A���{�������ɕ����̘H�����������邩�����ɂȂ邾�낤�B�i�����j
�Ō�ɖ��ɂȂ�̂́A���̂悤�ȓ��{�̊O��?���S�ۏ�헪����{�����ł����ɍ\�z���邩�ł���B���{�ɂƂ��Ď����I�Ȕ��f���A�\���ȍ����I�c�_���������܂܌��肳��邱�Ƃ͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��B���l�ȑI������O��ɁA�����I�ɕ������c�_���s���ł���B�͂����Ă��̂悤�Ȏd�g�݂����{�ɑ��݂���̂��B
�s���ɂ�����̂́A�s���w�҂̖q���o���w�E����A���@���������ݏo���u���ӔC�̐��v�ł���B�{���̊��@�哱�Ƃ́A�����܂Ŏ��b���\���I�ɐ���v�V��}����̂ł���B�Ƃ��낪��2�����{�����ɂ����Č����ɐi�̂́A��b�s�݂̂܂܁A�u�̈ӌ��v�����Ƃ��銯�@�������哱�I�������͂������Ԃł������B���ǂ͒N���ӔC�����Ȃ��܂܁A�e�Ȓ��̊Ԃɖ��C�͂����������Ƃ����B���{�O���̍\�z�͂�����錻�݁A�ӔC���鐭���I����̃��J�j�Y���̍Č����s���ł��낤�B
���E�͉����x�I�ɕ��G�����Ă��邪�A���G�Ȍ����Ɉ��|�����Ƃ��A�l�͂ǂ����Ă����Ԃ�P��������B�킽�������͍������A���G�Ȍ����G�Ȃ܂ܑ����A�_��ɍs���ł���A���Ȃ₩�Ȑ����I�m�������ׂ����B
���̂��߂ɁA��������c�_�����킵�A�������m�F���邱�Ƃ��K�v�ł���B���̎��]������ɍv���������B
�R�����g�F���c�ƍ���́A���{�̃g���̈Ђ���A��肽������B�����ɂ���Ă͈��{��肽���������B
2�{�ڂ͏T�Ԓ����i5.5�j�̐������̍߂Ɣ��A�É�Ζ��ł�
�u�h�C�c�ɂ����ē��{�ɂȂ��N�w�v����
4��15���A�h�C�c���E���������������B���q�͔��d��3��̉ҝX���~���ēd�͖Ԃ���藣���A����60�N�̗��j�ɏI�~����ł����̂����A���́A����͋����ׂ����Ƃ��B
�Ȃ��Ȃ�A�܂��AEU�̃J�[�|���j���[�g���� �̖ڕW��2050�N�����A �h�C�c�́A21�N�ɂ���� 5�N�O�|������45�N�Ƃ������ɍ����ڕW���f���Ă���B�����A22�N�̃E�N���C�i��@�Ń��V�A�Y�V�R�K�X�������}���B�G�l���M�[��@�ɒ��ʂ����B�ً}���I�ɐΒY�Η͂̉ғ��𑝂₵�A���߂ł͂��̔䗦��3�����x�܂ō��܂����B����ł��Ȃ��A�����P����������߂�38 �N�܂ł̒E�ΒY�ڕW��30 �N�ɑO�|�������V�����c�����͂�����ێ����Ă���B
������O��ɂ���ƁA �E�Y���̖ڕW��B������ɂ͌����̊��p�����Ȃ��������B���ɁA��N10�� �ɂ́A22�N���Ƃ����E�����ڕW��I�グ���A23�N 4��15���܂ʼn��������B 23�N����24�N�̓~����d�͎����Ђ����ɔ����Č����̉ғ�������ɉ�������Ƃ������_�����̌��ʂ��o�n�߂��B
�������A�h�C�c���{�́A4��15���ɒE�����������������B�����āA������ΒY�Η͂��ւ���d���Ƃ��čĐ��\�G�l���M�[�̔䗦��30�N��65���܂ň����グ��ڕW�Ɍ����đ���o�����B
����A11�N�̓����d�͕�����ꌴ���̎��̌�A���������͂���Ȃ��Ƌ����v�������������{�l�B����f���āA���{���{�́A�u�����ˑ��x���\�Ȍ������������v�Ƃ��Ă����B�������A�d�͂�����Ȃ��A�ȋ����オ��Ƌ������Ə����Ȃ�d���Ȃ��ƌ����ĉҝX���A�F�߂��B�����āA���╟���̂��ƂȂǂȂ��������̂悤�ɁA�ғ����Ԃ̉����⌴���V�݂܂ł��܂ތ������S�����H���ɑ�]�����悤�Ƃ��Ă���B
���Ƃ̊Ԃɂ���Ⴂ�͉��Ȃ̂��B
�ꌾ�Ō����A�u�N�w�v �ł���B�h�C�c��11�N�� 22�N���̒E���������߂����A�u�ϗ��ψ���v���J�Â����B�����ł̌��_���ȒP�Ɍ����A�u�����͗ϗ��I�ɋ�����Ȃ��v�Ƃ����l�������B�����́A���p������̂ɂ͑傫�ȗ��v��^���邪�A���̂��N����Ɨ��삵�Ă��Ȃ��n��̐l�X�ɂ����Ԃ��̂��Ȃ���Q��^����B���Ȃ̗��v�̂��߂ɑ��҂��]���ɂ���̂́A�ϗ��I�Ɉ��ł���B�܂������̏o���j�̂��݂̓h�C�c�����ł͏����̌��ʂ����Ȃ���������ɂ܂ŕ��S��摗�肷�邱�ƂɂȂ�B��������ȓI�ȍs�ׂŗϗ��I�ɋ�����Ȃ��B���� �ł���A�~�߂�Ƃ����̂��������I�����B���̓��͌��������A���������Ď��g�߂A�C�m�y�[�V�������i�ݎ����ł���\���͂���B�Ȃ�A���̓���˂��i�ނׂ��B���ꂪ�E�����̍��{�I�ȓN�w�ł���B������A�E�N���C�i��@�ł��A����������Ƃ��V�݂���Ƃ����c�_�͑S���o�Ȃ��B��������1�N��2�N�ғ��������邩�ǂ����Ƃ����c�_���o�邾���Ȃ̂��B
���{�ɂ͐����ɂ������ɂ����������N�w���Ȃ��A �n�k�Ɏア���������ƂȂ��������A�j�̂��݂������ł��Ȃ����Ƃ�m��Ȃ��疟�R�Ɖғ��������B
�����ˑ��̂������ŁA �Đ��\�G�l���M�[��E�u�i�d�C�����ԁj�̕���ŁA���E�̃C�m�y�[�V���������ɔs��AG7�ł́A ���g�������i�̑����������邨�ו��ɂȂ����B
�E�����́u�N�w�v�������鐭���Ƃ����o�Ă���̂��B����ɂ͉�X���������m�ȓN�w�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����B
�E�X��N�A�����������͕֗��B
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6461568
�R�����g�F�����̐ӔC�͈�ؔF�߂Ȃ��B2�S���̌��i�}��������Ƃ�F�߂Ă���̂ɁB
���@�͉��������Ă���̂��B�Ȃ������Ƃ����͉������Ă����Ƃ��߂��Ȃ��̂��B���d�����d�̕��������������Ƃ����̂ɁB
�E�w�����́A3�ɕ���B
https://news.yahoo.co.jp/articles/c0a8cc7bcc28be3e6ccc09d14e7e838ddfd6f12d
�R�����g�F�ǂ�ȗ͂����҂��������̂��B���ꐄ�i���u�̖���A�ُ�ȋC�ۂ̂����Ƃ͎v���Ȃ��B�������k���N���͕ʂɂ��āiUFO���܂ށj�A�O������̑傫�ȗ͂��|�������������͊ԈႢ���Ȃ��B���̎����A����ނ�ɂ��邱�Ƃ����͋�����Ȃ��B
�E�������̃g���`�E���A�l�̂̉e���Ȃ��̓t�F�C�N�B
https://news.yahoo.co.jp/articles/3e30da6a84f82ac9680ec73ac6ea2ec338dbf634
�֘A�L���F���������t��24�N�ȍ~�B
https://news.yahoo.co.jp/articles/3380940b66723c635a20dc59ba595458f11370bb
�E��U�葱���̂i�A���[�g�B
https://www.yomiuri.co.jp/column/politics01/20230426-OYT8T50029/
�ENHK�̃j���[�X������C�ɂȂ�Ȃ��B�㐼�B
https://www.asahi.com/articles/ASR4P6DD0R48UCVL007.html?iref=comtop_Topic_01
�E�n�}�̃h�����J�W�m��j�~�B�����͂�肽������B
https://www.tokyo-np.co.jp/article/246804
2323.�݂�E�����E�͂Ȃ��@5/1
�����Ȉ��{�����s�����َ����ɘa�ŁA�x�߂�҂͂܂��܂��L���ɁA�n�������̂͂܂��܂��n�����Ȃ����B�i���̐����͐��{�̏d�v�Ȗ����Ȃ̂ɁA�i�����B���x�T�w���Ǝv���Ă���j�����}�c���ɂ́A���̂悤�ȍl�����͂Ȃ��B���l�ς���ʎs���Ƃ͈قȂ�̂ł���B�����B���s���̏�ɌN�Ղ���x�z�҂��Ɗ��Ⴂ���Ă���B�ڂ̑O�̌��������悤�Ƃ͂��Ȃ��B�������咣����҂́A�݂�ȋ��Y�}���Ƃ݂Ȃ��B���̕��s���A�c�ݐ������{�̎x���̂ǂ��ɖ����`���c���Ă���Ƃ����̂��B���{�Ńv�[�`���Ɉ�ԋ߂������Ƃ́A���͎����}�̒��ێ�c���i���{�h���j�ƈېV�⍑������̋c���ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�����Ƃ͌`�̏�ł́A�I���őI���̂ŁA�I�����Ԓ������́A�����ɛZ�т�B�Ƃ��낪�I�����I���A�����Ȃǂ͊ᒆ�ɂȂ��B�o�c�ҁi���x�T�w�j�������Ă��Ȃ��B��ʎs���͔�ٗp�҂ł���A��Ђ̌o�c���͂Ȃ��B������В���}����A�Ј���}���������R�ŁA�����������B�X�̍�����ɂ���K�v���Ȃ��B�����畽����l���������o���ƁA�I���Ɍ��Ȋ�����ăA�J�Ă�肷��i����������j�B�����͊����ŁA�I���őI�ꂽ��ł͂Ȃ�����A��w�̂��ƁA�����͓�̎��A�O�̎��ɂȂ�B�ł͍����̖����͒N�Ȃ̂��B����͖{�����f�B�A���낤�B�Ƃ��낪���f�B�A�̎Ј����ق��̐g�B�����Ƃ��В��Ɉ��͂����������ɏ]���B�����猋�ǁA�����ɂ͖��������Ȃ��B���ꂪ�A���{�̐����̂���̂܂܂̎p�ł���B
�l�Ԃ���������Ƃǂ��Ȃ邩���A��X�͌��Ƃ����قǖڂɂ��Ă���ł͂Ȃ����B�E�N���C�i�̐N�U�͌����܂ł��Ȃ��A�~�����}�[�ł͍������s�E�A�X�[�_���ł͌R�����m�������B�č��ł��A�g�����v�̎��́A���x���Ђ�Ђ₵���B�_�Ȃ�ʐg�ŁA��ɗ�Â�ۂ��A���������ʂ��āA�������R���͂��������ƂȂǏo����͂����Ȃ��B����ɂ���悤�ɁA���͂Ďv���オ��A��������i���j�ƒ��荇��������A���Ղɕ��͂��s�g���āA���̌��ʁA���W�Ȏs�������𗎂Ƃ��B������R�k�������l�ނ������c�铹�Ȃ̂ł���B
�����V���i4.30�j�����J���ŁA�w�u�݂�E�����E�͂Ȃ��v�����ǂ�A�}������A�͂т���ޏk�A�������̌��_�͎��R���x�A�Ƃ�������L�����f�ڂ��Ă��܂��B���ǔ��̃W���[�i���X�g��J���G�i�\���ʕs�𗝁A��܂�ΎЉ�s����Ɂj�ƁA���m�g�j�L���X�^�[�̍��J�T�q�i��������鎩�ȐӔC�A���グ��l�֖���j����e���Ă��܂��B����ɐ��ޕs���R�̖ځA�p�ւ������A�Ƃ���A�����ɂ���܂Ő��������_�ɉ�����悤�Ƃ��A�܂��͒e�������݂Ă��������A����Ŏ��ׂ��ɏЉ��Ă��܂��B�����K�ǂ̋L���ł���A�����₩�ȃv���C�x�[�g�E�W���[�i���Y�������C����v�s�v�ɂƂ��Ă��i�v�ۑ��łł��B
����̑O�����́A�����V���А��i4.30�j�u����A�o�ɘa�A�E������͗e�F�ł��ʁv�ł��B���Ԋ�Ƃ̌o�c�̂��߂Ɍ��@������Ƃ����A�����Ă͂Ȃ�Ȃ����{�̖\���ւ̌x���ł��B���{�̕ێ琭�����A�@�����Ƃ��A���a���@���A�Ƃ��Ƃ������܂ő����Ă��܂����̂��Ɛ�債�܂��B�E�X�������߁A���܂�Ƃ����m��ʂ�ݓc�����A���a���{�̏�������@�ɕm���Ă���̂ł��B
���ە������������镐��̗A�o���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���̐����́A���@�ŕ��a��`���f���鍑 �̍����ł���B�E���\�͂̂��镐��̒ɓ����J�����Ƃ́A���N����Ă��������ɔw�����̂ł���A�e�F�ł��Ȃ��B
�h�q�����ړ]�O�����̉^�p�w�j�������Ɍ������A�����A���� ���}�̎����ҋ��c���n�܂����B ���{����N���ɉ��肵�����ƈ��S�ۏ�헪���A�ړ]�́u���i�v���f���A���������߂Ă����B
���݂̉^�p�w�j�ł́A�u���S�ۏ�ʂł̋��͊W�����鍑�v�ɗA�o�ł��鑕���i���A�~��A �A���A�����A�Ď��A�|�C��5����Ɍ����Ă���B����ɒn�������⋳��P���Ȃǂ������悤�Ƃ����c�_�͗����ł���B
�������A�퓬�@���q�͂Ȃ� �E���\�͂̂��镐��ɑΏۂ��g�債�悤�Ƃ����A���{�⎩���}���̈ӌ��ɂ͂��݂��Ȃ��B���{�͐��A�C�O�ւ̎x���͔�R���ɓO���A����A�o���������������Ă����B���a���ƂƂ��Đςݏグ�Ă����M�p��O����̋��݂��������ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B
���{�͕���A�o��ʂ��āA�F�D���ƈ��ۏ�̋��͊W���[�܂�A�͂ɂ�����I�Ȍ���ύX �̗}�~�ɂȂ���Ƃ����B�O���ɂ���̂͒����ł���A�E���\�͂̂��镐��̒ɂ܂œ��ݍ��߂A�������Ēn��ْ̋������߂鋰�ꂪ����B
�����}�͍�N4���̈��ے̒��ŁA�E�N���C�i���ɋ����A�u���ۖ@�ᔽ�̐N�����Ă��鍑�v�Ɂu���L������̑����v��n����悤���{�Ɍ��������߂��B�E�N���C�i�ɂ͖h�e�` ���b�L��w�����b�g�Ȃǂ𑗂��Ă��邪�A�E���\�͂̂��镐���O���ɒu�������̂��B
�}�~�̂��߂ł͂Ȃ��A���ł������Ɏg���邱�Ƃ�O��ɂ�������̋��^�́A�O�����̐��_�Ƃ͑�����Ȃ��B�ݓc�� �E�N���C�i�K��̍ہA�u���{�Ȃ�ł͂̎x���v�𑱂���ƕ\�������B�����▯���̕���ŗ͂�s�����ׂ����B
����A�o�g��̂�����̑_���́A�h�p�Y�Ƃ̈ێ��E�������B�[���悪���p�������ł́A��������ʂɂ��R�X�g�_�E���͐}�ꂸ�A���Y��Ղ���肫��Ȃ��Ƃ����킯���B���a���ƂƂ��Ă̌����Ȃ����Ȃ��A�h�q�Y�Ƃ��x�������ɂ����A�m�b���i��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
����̌��������A���̐��x�ƘA�����Ă��邱�Ƃɂ����ӂ��K�v������B�r�㍑�̌R���x�����鐭�{���S�ۏ�\�͋����x��(OSA)���A����Ŗ��c���̖h�q�Y�Ǝx���@�Ăɐ��荞�� �ꂽ�A�o���㉟������d�g�݂��A�O�����̉^�p���ς��A����ɉ����Ē��g���ς��B�E ���\�͂̂��镐�킪���ւ����A���̉e���͍L�͂ɋy�Ԃ��Ƃ����܂��˂Ȃ�Ȃ��B
�֘A�L���F���{�̐����M�����Ă��Ȃ���55%�B���������B
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6461769
�E���ꋳ��y�n�w���B�P�ޖڎw���c�̐ݗ��B�����s�B
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6461783
�R�����g�F�c�̂�ϋɓI�ɉ����������B��t�i�ٌ엿�̑����Ɂj���������B
�E��Ôg�̑���ז������j�����B�˂��Ȃ���ꂽ���X�N�]���B
https://news.yahoo.co.jp/articles/fdac555b6f1580068049ec29d1c35ed0eaa05c07
�E�ܗւ̐l����P��35���B���I���Ƃ𐅖c�ꂳ���鍑�Ɠd�ʁB
https://news.yahoo.co.jp/articles/68d1495373f7830cbedbc89602ba465d83dd1ea4
�E��������]�ސE��W�B
https://news.yahoo.co.jp/articles/d8035351f42a291565b9c6e78052007a8b36f86c
2324.�����ɔ��@5/4
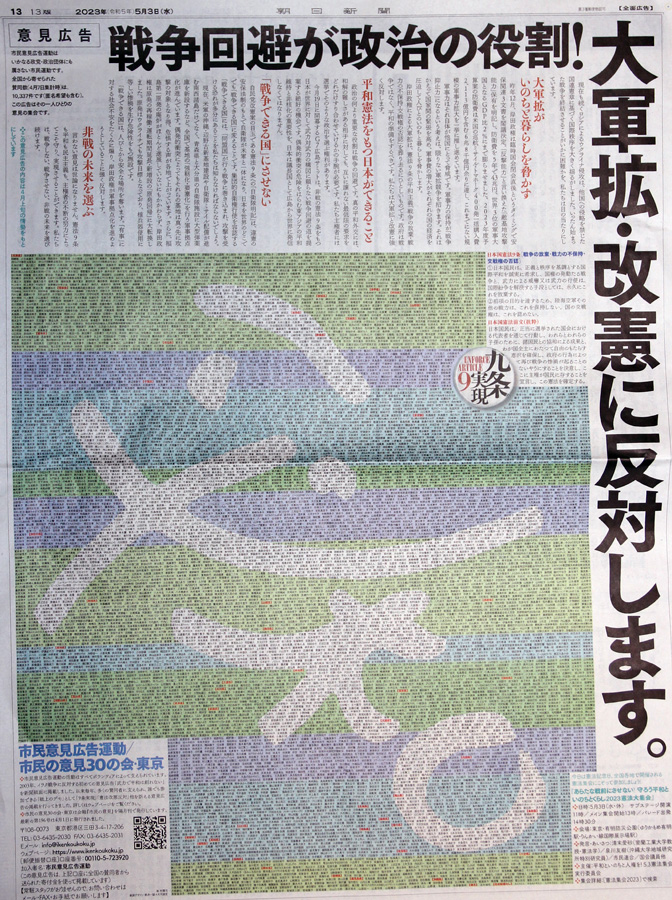
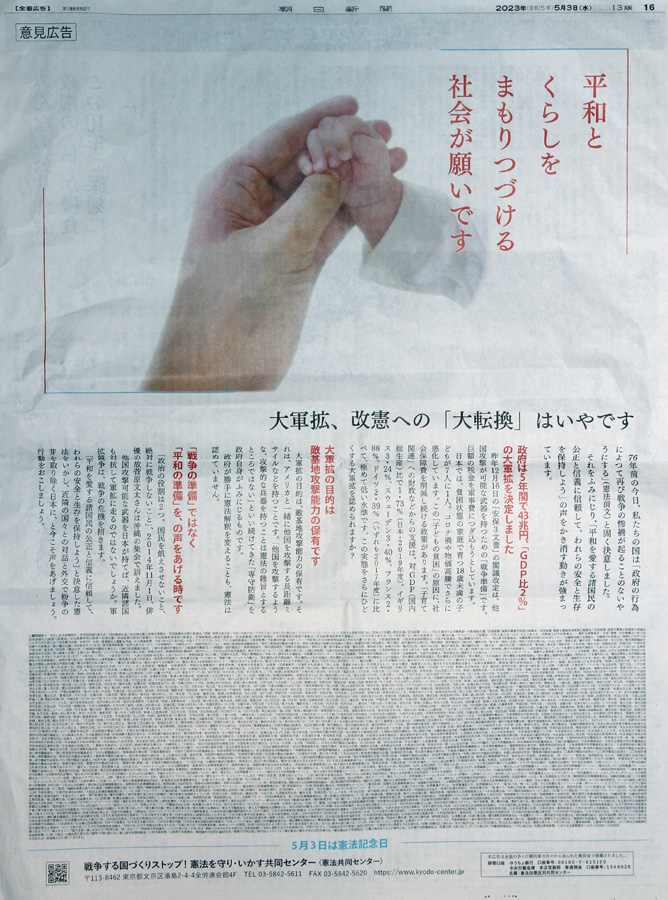
�������A�I�s�j�I�����t�H�[�����u���ܓ��{�̗�����`�́v����z��C���^�r���[����
�u�݂�Ȃ̌����Љ�A�����́w���x���N�H�A����10�N�Ő[���Ɂv
���{�����@�͎{�s�̓�����76�N���}�����B�u��@�v���������A�ݓc�����͈��S�ۏᐭ��̑�]����i�߂�B���@9���̉��l�����܁A�ǂ��l����ׂ����B���{�̗�����`�̉ۑ�͉����B����ǐ��̕������L���鎞��ɁA���@�����҂̔���z��E������w���_�����́A�u�ݖ�̍\�z�́v������Ƃ����A��l�����Ɋw�ׁA�ƌ��B
�\���{�����@���߂���ŁA�������͍��ǂ�ȉۊ������Ă���̂ł��傤���B
�u���낢��Ȍ����͉\�ł��傤���A�����̐��E�Ői��ł��� �w�q���r�́q���r���x�Ƃ�����肪�[�����ƍl���Ă��܂��v �iwtw���F�����̎������ƌ����Ē��������j
�\�ǂ������Ӗ��ł��傤���B
�u�w���x�̗̕��Ɂw���x�𑗂荞�ށA�Ƃ����Ӗ��ł̂��Ƃł��B�ߑ㗧����`�́A��l�ЂƂ�̌l�������炵�������Ă������߂ɁA���҂ƂƂ��ɂ��悢�Љ�����Љ������Ă������Ƃ���v���W�F�N�g�ł��B�قȂ�l���������l�X�����ɐ����Ă��������ŁA�w���x�Ɓw���x�̗̕���蕪���邱�Ƃ�����I�ɏd�v�Ȃ̂ł��v
�u�Ⴆ�A�ߑ㗧����`�̗�������ޓ��{�����@��15���́A�w�������x��S�̂̕�d�҂ƒ�߂Ă��܂��B�����ɂ��������l�����͌����Љ�̂��߂ɕ�d������̂ŁA�w���x�Ɏd������̂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł��B�܂��Ɂw���x�̗��O���\��Ă��܂��v
�u�Ƃ��낪����10�N�]���U��Ԃ�ƁA���{�������Łw���x�̗̕��ɑ���т�Ɂw���x�����肱��ł��܂����B�w���x�́w���x�����ے�����o�������A�X�F�w���ւ̍��L�n���p����v�w���̏b��w���V�݂̖��ł����B�����Ȃ̌������������ł͎��E�҂����o�܂������A�S�̂̕�d�҂Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�����S���҂́w���x�̂��߂Ɍ����L���g��ꂽ���Ƃւ̍R�c�Ƃ����Ӗ��������̂ł����v
�\�����̋敪�Ƃ����A���@�̊�{���[�������Ă���A�ƁB
�u�����ł��B������A���߂��Ȃ��̂́A���{�W�O���̌�ŎƂȂ鐛�`�̊��[�����i�����j�̔����ł��B�����Y�u�E���ꌧ�m���i�����j�������Ŗ��炩�ɂ��Ă��܂����A�������������ɉ���̋ꗣ�̗��j�𗝉����ė~�����Ƌ��߂��Ƃ���A�w���͐�㐶�܂�Ȃ��̂ł�����A���j�������o���ꂽ�獢��܂���x�Ɣ��������Ƃ����̂ł��v
�u�����̐��E�ɐg��邢�Ă���̂ɁA�w���x�Ƃ��Ă̎����̗��j�ɑ���v��������Ȃ���A���_�S��ӔC�ӎ����������Ȃ��B�����̋ߌ���j�ւ̊ۂ��Ƃ̖��S�C�Ō��ɂł���̂́A�w���x�̂��߂Ɂw���x�̗̕��ł���͂��̐������g���Ă��邱�ƂƓ����ŁA������́w�q���r�́q���r���x�ł��傤�B�݂�Ȃ̗̕��ł���͂��̌����Љ�A�w���x�ɂ���ĐN�H����Ă���̂ł��v�iwtw���F���[��������̖\���A�����ւ̔w�C�s�ׂ�����B�w�p��c�̔r���������̈�j
�\���{�����́A�W�c�I���q���͔F�߂��Ȃ��Ƃ��钷�N�̐��{���߂�ύX���A�e�F�ɓ��ݐ�܂����B�u������`�ɔ�����v�Ƃ��Ďs���̍R�c�̓������L����܂������A���܁A�ǂ����Ă��܂����B
�u2014�N����15�N�ɂ����āA�W�c�I���q����e�F�������S�ۏ�֘A�@�Ăւ̍R�c�̐������܂�܂����B������ӂŘA���N������R�̓����́A��҂��͂��ߐl�X�̎��Ȕ����I�Ȃ��̂ł����B�܂��Ɍ��m�����l�͂��Ȃ��������Ƃ��L�����Ă��܂����A���͋��̏�ɏ��A�}�C�N������܂����v
�u�ł͂��܁A���̎��̎c��͂Ȃ��Ȃ��Ă���̂��B�����̔M�C��U��Ԃ�ƁA�Y�ꋎ��ꂽ�悤�Ȋ��o���N�������܂��B����ǂ��A�ق��͎c���Ă���B�����ē��ݏ�����Ă��܂����킯�ł͂Ȃ����Ƃ����͒m���Ă��܂��v
�\�ݓc�����̉��œG��n�U���\�́i�����\�́j�ۗ̕L���t�c���肳��A���@9���̐��h�q�̗��O����E�����^�O������܂��B���{�������ł̏W�c�I���q���̗e�F�ɂ���āA�������O��Ă��܂������ʂł͂Ȃ��ł��傤���v
�u14�N�A15�N�����̎s���̍R�c�̊����͊m���ɁA����ȍ~�̐����ɂ͔��f����܂���ł����B���������Ӗ��ł́A�����锽�ΐ��͕͂������̂ł��B�����}�����͂��̌�������I���̂��тɏ������A�������ێ����Ă��܂����B������F�߂Ȃ��Ƌc�_�͑O�ɐi�܂Ȃ��v
�u�������A�����̎s���̊��������ʂ������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B������x���f���邱�Ƃ͂ł���B���̎�̂ɂȂ����̂͌����ē��݂Ԃ���Ă͂��Ȃ��Ƃ����F���������Ƃ��������x�A�����߂��͂͏o�Ă���͂��ł��v
�\�G��n�U���\�͂��߂���A�u���@9���͎��v�Ƃ����������������悤�ɂȂ�܂����B
�u�́A����ɐ�������A����͂��Ȃ��B9���́w���x������ꑱ���Ă��܂������A�����Ă��Ȃ��Ă������Ȃ܂łɁw���x����Ă����킯�ł͂���܂���B������ٔ��̏�Ȃǂŗl�X�Ȏ咣���߂��鑈�����J��L�����Ă������j������̂ł��v
�u���N�푈����x�g�i���푈�A �A�t�K�j�X�^���푈�A�C���N�푈�ւƑ������ŁA9�����Ȃ���Γ��{�͂ǂ�ȑI�������Ă����̂��A�z�����Ă݂Ă��������B���O�ƌ����̖�ْ̋��ɔ��ė��O���̂Ă�̂��A���O�ƌ����̊J����O�ɂ��ĂȂ����O�������ɋ߂Â��悤�Ƃ���̂��B�����Љ������Ă����̂ł��鎄������l�ЂƂ�̈ӎu���A�����Ɩ��ꑱ���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���v
?���V�A�̃E�N���C�i�N�������������ɁA�U�߂�ꂽ�Ƃ��Ɂu9���͖��ɗ����Ȃ��v�Ƃ������������L�����Ă��܂��B
�u������A�Ē����푈���N��������A�ǂ��Ȃ�܂����B�����͂��݂��ɂ��ꂼ��̖{�y�������Ȃ�U���͂��Ȃ��ł��傤�B���{�ŕĒ��̗����̒e����ь������ƂɂȂ邱�Ƃ͂悭�悭���o���Ă������ق��������v
�u�W�c�I���q���̍s�g���f���A����ɓG��n�U���̈ӎv�Ɣ\�͂����ɂ��āA�A�����J�Ƃ̌R�����͂𖾗Ăɂ������قǁA���{��G�ɂƂ��Đ�Ђ̃��X�N�͍��܂�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B9�������������炱���A���̓��{���A�W�A�̏����ɗ^���鋺�Ђ������炵�A���R�g�����̔j�ǂɊׂ邱�Ƃ��Ƃ��������}�~���Ă����A�Ƃ������Ƃ͋q�ϓI�Ȏ����Ƃ��Ēm���Ă����ׂ��ł��v
�\���E�I�Ȉ��S�ۏ�����ω��������Ƃ������A�u�����ɑΉ�����ɂ͂��ꂵ���Ȃ��v�Ƃ������c�_�����s���A���ې���̓]�����i��ł���悤�Ɍ����܂��B
�u���̎��ケ���A�����ǐ��ł͂Ȃ��A�ݖ�̍\�z�͂����߂��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���v
�\�ݖ�̒̑z�͂ł����B
�u���{�Ɠ�����2�����E���̔s�퍑�ł���h�C�c�̓N�w�ҁA�����Q���E�n�[�o�[�}�X���̊�e�����{�ł��Љ��Ă��܂��B���틟�^�ƕ��s���Ē����ւ̓w�͂����߂�悤���߂���e�ŁA�w�܂��܂������̋]���҂��o���푈�𑱂���̂ł͂Ȃ��A�䖝�ł���Ë����f�Ƃ��Ă��Nj����邱�Ɓx������Ă��Ă��܂��v
�u���̊�e�́A�E�N���C�i�R���x���Ō��������߂悤�Ƃ��鐼���̐����Ƃ���Ƃ����̖ڂɂ́w��펯�x�ɉf�������Ƃł��傤�B�w�ǎ��x���w�펯�x�̑�َ҂̂悤�ȑ��݂ł���n�[�o�[�}�X�����A�����ɂ������Ƃ������Č����A�w��펯�x������̂ł��B�L�͎����A���̘_�l�ɑ傫�ȃX�y�[�X�����B���������m���l�̎��H�m�ƃ��f�B�A�̌����������� ���邱�Ƃ��ł��܂��B�ݖ�̍a�z�͂Ƃ͂����������̂ŁA�����������{�̋ߌ���j����w�Ԃׂ��ł��v
�\��̓I�ɂ͂ǂ��������Ƃ� ���傤���B
�u���X�R�����グ�܂��傤�B�ނ�1911�N�ɓ��m�o�ϐV��Ђɓ���A�w�R����`�A�ꐧ��`�A���Ǝ�`�x�ɑR����w�Y�Ǝ�`�A���R��`�A�l��`�x������_�w��S���A��������ɂ��闧��ɂ��܂��B�a�ɂ��Z���ԂɏI���܂������A�Ƃ��Đ�㎩���}������S�����ƂɂȂ�����吳10�N�i1921�N�j�ɏ������_�����A�w�������̊o��x�ł��v
�u��1�����E���̐폟���ł�����{���A�ǂ�Ȏd���Łw�ꓙ���x�ƂȂ邩��_�������͂ł��B ���́A�w����{��`�̌��z�x�����߂āA�A���n�̕�������܂��B��ɐA���n�x�z���L���Ă�����i���ł���p����č��́A���{�������I�U���ɏo�邱�Ƃɂ���āA�w�ꋫ�Ɋׂ�x�ƌ������̂ł��B�ݖ�ł��邱�Ƃ����݂ɂ����A�����ǐ��łȂ��\�z�͂��݂邱�Ƃ��ł��܂��v
�u��@������邩�炱���A���̎���ɂ��A���{���u����Ă���n���w�I�Ȏ�_���t��Ɏ��\�z�͂����߂��Ă��܂��B�Ⴆ�A���j�Ƃ̉����z�q���A�����V���̃C���^�r���[�ŁA�w�Η����钆���ƕč��̊Ԃ�3��L���̒����ɂ킽���Ĉʒu���Ă��邱�Ƃ́A�����̕��a�ɂƂ��Ă��傫�ȈӖ�������͂��ł��x�Ɠ����Ă��܂��B���������ݖ�̍\�z�͂��K�v�ł��B�����ēǂ��Ă��̒m�b�Ɗo������߂Ď��������̂��̂ɂ���B��l�Ɋw�Ԏp�������܉���苁�߂��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���v�i������@�L�G��)
�R�����g�F�Ȃ�Ɠǂ݂₷���A������Ղ��C���^�r���[�ł��邱�Ƃ��B
�������A�����̒����V���̎А��̖��������ł��B
�u���a���@�ƈ���3�����A�����`�̌`�[��������ʁv
�c�u���a���Ɓv���x����K�������X�ƍ������ƂȂ�A�ώ������˂Ȃ��B�������A���ꂪ�A���X�N���܂߂����J���ƁA�٘_�ɂ������������J�ȋc�_�����ɐi��ł��邱�Ƃ͌��߂����Ȃ��B
���ӌ`���̓w�͂����K�v�B�e���~�T�C���̔��˂��J��Ԃ��k���N�B�}���ȌR�g��i�߁A�͂ɂ�����I�Ȍ���ύX�����Ƃ�Ȃ������B�����āA���V�A�ɂ��E�N���C�i�N���B
���{����芪�����ۊ��̌������������Ă��A�G��n�U���\�͂ۗ̕L�ɂ��A�h�q��̑啝���ɂ��A�^�����鍑���͏��Ȃ��Ȃ��B�����A�s���ɏ悶�邩�̂悤�ɁA���{�����ӌ`���������Ȃ�ɂ�����ɉ�������̂��B
�E�N���C�i����A���B�e���͈��ې���̌������𔗂�ꂽ�B���{�Ɠ������A��̐푈�ɑ��锽�Ȃ���̍��Â���̑b�Ƃ���h�C�c�́A�����n�ɕ���𑗂�Ȃ��Ƃ��Ă���������]�����A�E�N���C�i�w�̕��틟�^�ɓ��ݐ����B
�h�C�c�o�g�Ő�䔒�S�����q��w�ō��ۊW��������}�X���[����́A�h�C�c���{�̑Ή��ً͋}�[�u�Ƃ��ė����͂ł���Ƃ��A���L�����ӂ����鎞�Ԃ��Ȃ������Ǝw�E����B
�u�����̗����Ȃ��ɐi�߂�A�����`�̎�̉��������B ���ӌ`�����Ȃ��ƁA�x�������N�����Ē��������Ȃ����A�ɒ[�Ȏ咣�����鐭�����͂̑䓪���������������B���ʓI�Ƀ��V�A�̎v���ڂɂȂ��Ă��܂��v
�����ׂ��́u�G���v����ł͂Ȃ��B���{��������c�_���y�A���@���匠�҂ƒ�߂鍑����u������ɂ����܂܁A���̑厖�Ȍ��������X�ƕς��Ă����B�^�ɋ����ׂ��́A�����`�̌`�[���ł���B
�֘A�L���F76�N�O���炠�����A���@���������ɂ̋C������B���{�l�͈ӎ��̊o���K�v�B
https://www.tokyo-np.co.jp/article/247631
�֘A�L���F�ݓc�C���������A�ܗ������B�c�_�g�U�B
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023050200806&g=pol
�֘A�L���F��������47%�B
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6462099
�R�����g�F�ǔ��̒����ł͎^����61%�����A���f�B�A�̉E�X���̑��{�R�A�ǔ���M�p����ƌ������ɖ���������B���f�B�A�ɂ�鐢�_����́A�܂Ƃ��ȃW���[�i���Y���Ȃ��ɂ���Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��B���͂̎��Ƃ��āA���{�̃W���[�i���Y���̗ǐS�������܂Ŕj���Ɛl�͒N�Ȃ̂��B���ꋳ��̘��S�ɐ��艺�������݂ƈ��{�̖��F�i�x�c�l���B���������̗L�u���W�߂���A���͎����Œ����́A�Ƃ�����蕽�a�������鍑���ׂ̈̃��x�����Ȑ��_�����@�ւƃ��f�B�A�𗧂��グ�����B�����͎Ԃ��č�邵���Ȃ����A�����}�W�ł���B���ł̋͂��ȋ~���́A�ǔ��̖{���n�ŁA�������ېV�ɋ��蕉���Ă��鎖�����A�ېV�͎v�z�I�ɂ͎����Ɠ����v���X��㏤�l���B�Ƃ�����肳��ɉE���Ȃ̂ŁA������A������ׂ���V�i���ł͂Ȃ��A�����炭�n�ʂƌ��́j�ƈ��������ɁA�����ɐQ�Ԃ�i�����ł͎����𑀂���肾�낤���j���Ƃ��Ȃ��ƒf���ł��Ȃ��B���{�̖����`����芪����������A�܂����O�̈ӎ����ǂ��̏ɂ���B�����������B���ǂ�ȏɒu����Ă��邩�̈ӎ������Ȃ��B���ʁA�����}�̐ꐧ�ƍِ����̈ӂ̂܂܂ɁA�B�X���X�Ɨr�̂悤�ɏ]�������B�����S�āA��~���ŗD��̎x�z�w���x�T�w���o�c�ҁ������Ɓ��@���c�̊����i���ꂼ��ꕔ�Ɗ����Č����Ă����j�A�v���X�ېg���S�ĂŁA������l�ԂƂ��v��Ȃ������i���ǂ�����A���łɐ��_�a�@���j�B���͎҂ɐK����U�郁�f�B�A�B���s�̌����s�����L���㗝�X�B�����̍\���̂ǂ��ɎЉ�`�A���a���@�A�l���A���R�A���������݂���Ƃ����̂��낤�B�������ɂ��Ă��I���^���ɂ��Ă��A�n�Ղ̂����A���}�̐��E�҂ɂ����Ή��ł����A�n�Ղ�������Ŕ��Ȃ��҂ɂ͎�����A�����ڂ͂Ȃ��A�������������h�u�Ɏ̂Ă邵���Ȃ��B�������҂ɂ���������̋@��͂Ȃ��悤�ȁA���݂̑I�����x�̉��ŁA�ǂ�����T�C�����g�E�}�W�����e�B�̖��ӂ�I���ɔ��f��������̂��B�����Ă��̑O�ɁA��̂ǂ�����Γ��{�̖��O�͈�[�̉��l�ƌ����ɖڊo�߂�̂��B�_��A���̕��@���͂ȉ��ɋ��������B
�E�k�C���V�����̃g���l���H���B�F�J�g�Ȃ�4�Ђ������̕B
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230503/k10014056661000.html
�R�����g�F�ŋ߂̑���Ƃɂ͏��Ɨϗ����ʗp���Ȃ��炵���B��Ƃ̃v���C�h���i�ʂ��������A�R���v���C�A���X�����Ȃ��B�ܗ֑��������āA�F�d�ʂɉE�֕킦�ł��������̂悤���B�ŋ߂̓��{�̌o�ς̒����ɂ́A�����������\�Ȗ����B�i���ʂ��Ȃ��̂ɖ�����V�����o�J�����j�����������������Ă���̂ł͂Ȃ����B�o�c�ҁi�܂ޖ����j�ƌo�c�̎��̒ቺ�i�\�͂̕s���Ɛl�Ԑ��̌������܂ށj���A�����ɂ��\��Ă���悤���B�����Ă��̔w�i�ɁA�����}�c���́A�o�c�҂���ƂƂ̖������A�_�Ԍ�����̂ł���B
�E�O���������ǒ��������ݓc�����B
https://www.jiji.com/jc/v8?id=20230428seikaiweb
�R�����g�F����߂ċ����[���̂ŁA��ǂ������߂������B
2325.�l�ԁA��������Ɓ@4/30
�����Ȉ��{�����s�����َ����ɘa�ŁA�x�߂�҂͂܂��܂��L���ɁA�n�������̂͂܂��܂��n�����Ȃ����B�i���̐����͐��{�̏d�v�Ȗ����Ȃ̂ɁA�i�����B���x�T�w���Ǝv���Ă���j�����}�c���ɂ́A���̂悤�ȍl�����͂Ȃ��B���l�ς���ʎs���Ƃ͈قȂ�̂ł���B�����B���s���̏�ɌN�Ղ���x�z�҂��Ɗ��Ⴂ���Ă���B�ڂ̑O�̌��������悤�Ƃ͂��Ȃ��B�������咣����҂́A�݂�ȋ��Y�}���Ƃ݂Ȃ��B���̕��s���A�c�ݐ������{�̎x���̂ǂ��ɖ����`���c���Ă���Ƃ����̂��B���{�Ńv�[�`���Ɉ�ԋ߂������Ƃ́A���͎����}�̒��ێ�c���i���{�h���j�ƈېV�⍑������̋c���ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�����Ƃ͌`�̏�ł́A�I���őI���̂ŁA�I�����Ԓ������́A�����ɛZ�т�B�Ƃ��낪�I�����I���A�����Ȃǂ͊ᒆ�ɂȂ��B�o�c�ҁi���x�T�w�j�������Ă��Ȃ��B��ʎs���͔�ٗp�҂ł���A��Ђ̌o�c���͂Ȃ��B������В���}����A�Ј���}���������R�ŁA�����������B�X�̍�����ɂ���K�v���Ȃ��B�����畽����l���������o���ƁA�I���Ɍ��Ȋ�����ăA�J�Ă�肷��i����������j�B�����͊����ŁA�I���őI�ꂽ��ł͂Ȃ�����A��w�̂��ƁA�����͓�̎��A�O�̎��ɂȂ�B�ł͍����̖����͒N�Ȃ̂��B����͖{�����f�B�A���낤�B�Ƃ��낪���f�B�A�̎Ј����ق��̐g�B�����Ƃ��В��Ɉ��͂����������ɏ]���B�����猋�ǁA�����ɂ͖��������Ȃ��B���ꂪ�A���{�̐����̂���̂܂܂̎p�ł���B
�l�Ԃ���������Ƃǂ��Ȃ邩���A��X�͌��Ƃ����قǖڂɂ��Ă���ł͂Ȃ����B�E�N���C�i�̐N�U�͌����܂ł��Ȃ��A�~�����}�[�ł͍������s�E�A�X�[�_���ł͌R�����m�������B�č��ł��A�g�����v�̎��́A���x���Ђ�Ђ₵���B�_�Ȃ�ʐg�ŁA��ɗ�Â�ۂ��A���������ʂ��āA�������R���͂��������ƂȂǏo����͂����Ȃ��B����ɂ���悤�ɁA���͂Ďv���オ��A��������i���j�ƒ��荇��������A���Ղɕ��͂��s�g���āA���̌��ʁA���W�Ȏs�������𗎂Ƃ��B������R�k�������l�ނ������c�铹�Ȃ̂ł���B
2326.�n�C�u���b�h�Ɖu�@5/7
����̑O������TV�ԑg����ł��B
5/5�̕�1930�iBS161�j���A�ŋ߂̔ԑg�Ƃ��Ă͒��������ʂ���R���i�̘b������グ�Ă��܂����B
���̒n��̎��͂����m�炸�A��X���g�����݃I�~�N�������i8�g�j�̗��s�̍Œ��ɂ���̂ŁA�����[���������܂����B
�o�Ȏ҂͌����݂̓c���O���J��b�ƁA���ۈ�Õ�����w�̏��{�����ł��B
�܂������m���Ŕ�������9�g�́A8�g�ȏ�̑�g�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B
������I�~�N�������ł͒v�������Ⴂ�ƌ����Ă��A�����Ґ���������A���Ґ��͑����铹���ł��B
���̍ő�̗��R�́A���{�ł͎��R�Ɖu�����Ȃ��i���R���������Ȃ��j���ł��B
���{�ł̊����ɂ��R�ۗ̕L����42.3%�ŁA�p���̏ꍇ��86.1%�Ƃ̂��Ƃł��B
������6�J����̌��ʂƂ�����r�\������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@2��ڎ�@�����̂݁@�����{2��ڎ�@�@
�����\�h���ʁ@�@15.1% �@ 51.2%�@ 60.4%
�d�lj��\�h���ʁ@64.6% �@ 80.1%�@ 96.5%
���Ȃ݂Ɋ����Ɖu��20���6���A����҂�3���������ł��B
�����{2��ڎ���A�ŋ��̃n�C�u���b�h�Ɖu�Ɣԑg�ł͌Ă�ł��܂��B
�܂�2��ڎ�̌�Ŋ������Ă������������ł��B
�W�c�Ɖu�̈ێ��ɂ́A�����ɂ��Ɖu�ۗ̕L�҂𑝂₷�K�v������Ə��a��w�̓�؋����������Ă��܂��B
�G�Ȍ�����������A�������������ڎ���Ɖu�������Ƃ������ƂŁA�����ɐڎ킪�����ŋ��Ȃ̂������ł��B
�]���ĉ䂪�Ƃ̏ꍇ�́A���ɍŋ��̖Ɖu�����邱�ƂɂȂ�܂��B
���������������܂��B
�u�����\�h���ʂ̐��ځv
�@�@�@�@�@�@�@�@�@3�J����@6�J����@12�J����
�����̂݁@�@�@�@�@65.2%�@�@51.2%�@�@24.7%
�n�C�u���b�h�Ɖu�@69.0%�@�@60.4%�@�@41.8%
�u�d�lj��\�h���ʂ̐��ځv
�@�@�@�@�@�@�@�@�@3�J����@6�J����@12�J����
�����̂݁@�@�@�@�@82.5%�@�@80.1%�@�@74.6%
�n�C�u���b�h�Ɖu�@96.0%�@�@96.5%�@�@97.4%
�d�Ǘ\�h���ʂ̓u���b�h�Ɖu�ł͑������Ă��܂��B
������Ƃ����Ċ����𐄏������ɂ͍s���܂���B
���ꂱ���ċz��n���b�����̂�����ɂ́A���̊댯�����邩��ł��B
�������Ȃ��ɉz�������Ƃ͂Ȃ��̂ł��B�W�c�Ɖu�Ɋ��҂��邱�Ƃɂ͈Ӗ��͂Ȃ��̂ł��B�Ȃ��Ȃ犴���͌l�l�̖�肾����ł��B
����ł�����������A���̎������J�������āA����������ł͂Ȃ��Ɗ���邵������܂���B
�A�����̊����i�Ǐ�j�����z���邽�߂́i�������т邽�߂́j�w�͂��K�v�ɂȂ�܂��B
�����Ō����������Ƃ́A���{�̌����Ƃ͕ʂɁA�������g�̔��f������d�v���ł��B
�Ȃ��Ȃ琭�{�̌����́u���ĂɂȂ�Ȃ��v����ł��B
�}�X�N�s�v�Ƃ����Ɍ����Ă��A�����͎����̓����s���A��Ȃ����ȏꏊ�ɂ͋ߕt���Ȃ��A�����ōR���������s���Ȃǂł��B
5�ނɂȂ�������Ƃ����āA���������܂��ł͂Ȃ��̂ł��B�P�Ɏ����̔��f�i�Ɣ�p�j�őΏ����Ȃ����Ƃ������Ȃ̂ł��B
�A���������̂͑����f�Ë��ۂ�����A�x�b�h�̕s�������������ł��傤�B
�܂��h���×{�̌o���҂������Ă���悤�ɁA���a�R�̎��Â��m������Ă���悤�ł��B
�iwtw���F���a�R�̎��ÂƂ����̂́A�d�lj���\�h���邽�߂ɁA�R�̂𒍓����鎡�Âł��j����܂ł��e�ՂɈ�҂Ɋ|�����悤�ɂ��Ȃ�ł��傤���A�܂������Ȃ��Ăق����Ǝv���܂��B�A�����ɍ���҂͔N���̐ڎ����K�v������܂��B
���ǁA�ߓx�ɋ��ꂸ�A�ł����炸�����Ȃ��Ǝv���܂��B�Ƃ��낪���̐��Ԃ̕����͍������Ȃ��̂ɁA�������ꂸ�����ɂȂ��Ă���B�����炱��9�g�͕K������Ă���Ǝv���������ǂ��ƍl���܂��B
�Ȃ̂ŁA���͂�͂�6��ڂ̃��N�`���͐i��Ŏ悤�Ǝv���Ă��܂��B
���̂Ȃ�A�O5��̃��N�`���́A���ɗ\�h���ʂȂǂ́A�Ƃ����ɖ����Ȃ��Ă���͂�������ł��B����ɍ���҂̗͑͂��Ȃ��̂ŁA�y���Ǐ�ł��A�傫�ȕ��S�ɂȂ�\�������邩��ł��B
���ꂩ��ԑg�̌l�I�Ȋ��z�ł����A���݂̉������J�����A�����ɗ�W�ŁA�c���O��b�Ƃ͑�Ⴂ���Ƃ������Ƃ��ǂ�������܂����B�����ɂł���サ�ĖႢ�������炢�ł��B���{�������x�X�g�ł��B�����A�����R���i�E�E�H�b�`���O�ɂ͂����������܂����B�R���i���A���̐l���ł��傫�ȁi���́j�G�|�b�N�ł��邱�Ƃ����͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B
2327.5�ނ̉ۑ�@5/8
�����̑O�����͒����V���i5.7�j�̎А��ł��B
�w�R���i�u�T�ފ����ǁv�ɁA���Ԃ�o���ꂽ�ۑ蒼�����āx
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ��A��������G�ߐ��C���t���G���U�ȂǂƓ����u�T�ފ����ǁv�ƂȂ�B���E�ی��@�ցi�v�g�n�j���R�N�R�J���ԑ������u���ۓI�Ɍ��O�������O �q����ً̋}���ԁv�̏I����錾�����B
���ʂ͗��s���J��Ԃ��A�a�@�⍂��Ҏ{�݂ɂƂ��ċ��ЂƂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�̑����c��������Ȃ�A�\�f�������Ȃ��������B
�����ł̗��s�Ɏn�܂������A�E�C���X�̔������͂��܂����肳��Ă��Ȃ��B�V���Ȗ��m�̊����ǂ����ǂ��Ŕ�������̂��͗\�������Ȃ��B���C���t���G���U�̚M���ނւ̊��������E�e�n�ő������A�V�^�C���t���G���U�ւ̌x�������܂�B
�@
���J��Ԃ�����ÕN��
�u���v�ւ̔������m���Ȃ��̂ɂ��邽�߁A�܂��͂��̊Ԃɕ�������ɂȂ����ۑ�����邱�Ƃ��s�����B
���Ăɔ�ׂďd�ǎ҂⎀�҂�Ⴂ�����ɗ}�����Ƃ͂����A���s�̂��тɕK�v�Ȍ������ł��Ȃ�������A�x�b�h���s�������肷�鎖�Ԃ��J��Ԃ����B
�p���f�~�b�N���ɂ����Ɍ���ꂽ��Î��������A�������̂���Ԑ�������̂��B���̂��߂̌v��Â��肪�s���{�����Ƃɐi��ł���B
�a�@��f�Ï��̘A�g�͂������A�l��s���Ɋׂ����ی����̕��S���ǂ����U������̂����������K�v���B���Ԃ̌�����Ђ��ǂ����܂����p�������B
�d�ǎ҂��}������ΐl�H�ċz���W�����Î��i�h�b�t�j������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����B����͌����ɒ��ʂ������ł�����B
����ȂƂ��ɂ����D�悵�Ď��Â��ׂ��Ȃ̂��B���s���n�܂��Ă���ł͗��Q�����݁A���������߂�̂�����Ȃ�B�܂��Ă⌻��Ɉς˂�ׂ����ł��Ȃ��B��������l���������Ă������Ƃ��������Ȃ��B
��������̓��[�@����
�V�^�C���t���G���U���[�@�Ɋ�Â��ݒu���ꂽ����n���̑��{�����p�~�����B
�@
2021�N�́A���N�ȏ�ɂ킽���ċً}���Ԑ錾�̔��o�≄�����f���I�ɑ������B�E�������l���}���������ŁA���Z��x�Ƃ̗v���ɏ]��Ȃ��X�����R�Ƒ��݂����B�f��ق┎���قɂ͋x�Ƃ����߂A�����V���n�͉c�Ƃ��Ă��悢�Ƃ��������������������������Ȃ��ꂽ�B
�@
�錾�̂��ƂŔ�����ꂽ�s��������x�Ɨv���̑Ó����ɂ��ċq�ϓI�Ȍ��͂��܂�����Ă��Ȃ��B���@�ŕۏႳ�ꂽ�ړ���c�Ƃ̌����E���R�̐����́A�����̕����𗝗R�ɂǂ��܂ŋ��e�����̂��B���ɔ����邽�ߎ���I�ɂł������ׂ����B
�@
���[�@�́A���Ƃ��Ƃ͐V�^�C���t���G���U��z�肵�Ă������@�����B����ɋ}�����炦�ŃR���i��K�p�����ɉ߂��Ȃ��B���̂����A�Q��ڂً̋}���Ԑ錾�̂��Ȃ��ɂ͂킸���ȐR�c�Łu�܂h�~���d�_�[�u�v���V���ɂ���ꂽ�B
�C�O�ł͊O�o�����ւ̈ᔽ�Ȃǂɔ����̂��鍑������B����ɔ�ׁA�u���l�v��u�v���v���x�[�X�ɁA��l�ЂƂ�̋��͂ɕ����Ƃ��낪�����̂����{�̓������B�ɂ₩�Ƃ������邪�A�ӔC�̏��݂������܂��ɂ�����B
�}�X�N�̒��p���C�ӂ̋��͗v���Ƃ����ʒu�t�����B���ꂪ�ƊE�̎w�j�Ȃǂɗ��Ƃ����܂�A�����I�Ƀ��[���Ƃ��ċ@�\����B�K�͈ӎ��̍����A���O�q���ւ̈ӎ��̕\��Ƃ������邪�A�����Ɂu�������́v�Ƃ������t�ɏے������悤�ȑ��݊Ď��̏���ɂȂ��鋰�������B
�@
�ǂ�Ȑ��x�����{�ɂӂ��킵�����B��̎�������������A�[��������荂�߂�ɂ͂ǂ�������悢���B�c�_��[�߁A���ӂ�K�v������B
�������������ׂ��ӔC
��̎i�ߓ��ƂȂ�u���t�����NJ�@�Ǘ��������v���H�ɂ���������B�����哱�ŏȒ��c�����r����Ƃ̕��j�Ɉ٘_�͂Ȃ��B�����A���{�����ɂ��S����ċx�Z�Ȃǂɂ݂�ꂽ�ƒf�̊낤���͖Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B��̏��F�R���Ȃǂ̎葱���ւ̉�����T����ׂ����B
�@
���̊ԁA�[�u�̖ړI�┻�f�Ɏ���ߒ������{�̑����疾�m�ɔ������A�����Ƃ̊Ԃňӎ������L�ł������͐r���S���ƂȂ��B�Ƃ�킯�R���i�Ή��ōs���l�܂��đސw�����������̂��Ƃł͐[���Ȑ����s�M���������B
������}���A�Љ�o�ϊ������ێ�����œK�ȃo�����X�����������̂͗e�Ղł͂Ȃ��B
�ł�������A���j�̌��ɋC�t���A�����ɔF�߂Đ�����s�����A���Ȃ����ɐ������B���������������Ɍ����A�ӔC����̎p���ɏI�n�������Ƃ��s�M�̍���ɂ������Ƃ݂�ׂ����B����͏Ȓ����܂߂����{�S�̂ɒʂ���̎��Ƃ�������B
���ƂƂ̋��Ƃł��h����c�����B���j�����߂Ă���u���n�t���v�邽�߂Ɏ�������ɉ����A���{���S���ׂ����X�N�̐����킹���ʂ��������B���Ƃ̉�c�̂��A���s���n�܂��ċ}�������ꂽ���̂��B�Ƃ��ɗL���ɂ́A��蕪�쉡�f�I�ɐ��m�����W������K�v������B�ςݎc�����ۑ�����猟���A����̑̐��Â���ɐ������Ăق����B
�R�����g�F�咩���ɏ��˂��C�͖ѓ��Ȃ����A���̎А��Ɍ����ẮA�及�����̂��ꂢ���ƁA�����_�ɏI�n���A�������o�����A�f�Â���ꂸ�ɍݑ�ŖS���Ȃ��Ă������A����Ƃ��������̖��O�͈���ɓ`����Ă��Ȃ��B�f�p�ȍ����̖��ӂ���V�������p���ɁA�W���[�i���Y���𖼏�鎑�i�͂Ȃ��B���������Ă͉������A���ƃR���i�ƍ����̊W�ɂ��ẮA�����wtw�̃n�C�u���b�h�Ɖu�iBSTBS�j�̏��̕����A�y���ɍ����Ɋ��Y���A���ɗ����̂ƍl����B���������R���i��̍����ƒx��́A��t��A�a�@�A����ƊE�A���J�Ȃ̊������v���ő�̏�Q�ł��������Ƃ��Ȃ��w�E���Ȃ��̂��B�S�̎l�p�`�����Ƃ����Ȃ�����A�����ׂ̈̈�ÂȂǎ������Ȃ��B
�֘A�L���F�R���i���s�A����13���l���B
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6462509
�R�����g�F��ÂЂ������e���B
2328.�̏��40�N�@5/10
�����������ɖ₢������B��̎����͖�����������Ă���̂��B���X�Z����ʎ��Ԃ������āA�����ł��A�N�ɂł���ɓ��������ח��ĂĂ���B�����ɂ͉s�����͂��A�V�˂̂Ђ�߂����A���l�I�ȗ\�����A�⑫�̏���Ȃ��B�[�I�Ɍ����A�ꍂ��҂��A���ȏ����l�^�ɂ��āA��s����ׂĂ���B�ȍ�Ƃ̐ςݏd�ˁB�������ꂾ���̃T�C�g�ɁA�N�����Ԃ��������Ƃ��邾�낤�B���̃T�C�g�iwtw�j���u�K�₵�Ȃ��Ă��ǂ����R�v�͎R�قǂ���̂��B
���ɗ����Ȃ��Ƃ����ᔻ�����낤�ƂȂ��낤�ƁA�������͍��ۂ̍ۂ܂ŁA���́u���ʂŋ������v��Ƃ𑱂��邾�낤�B�Ȃ��Ȃ炻���ɂ́A����O�ցA�����ւƓ˂��������A�~�ނɎ~�܂�ʁA�}���������Փ������邩�炾�B���̃p���[�E�\�\�X�́A��������芪���Љ�ƁA�L�����E�ւ́A�s���邱�Ƃ̂Ȃ������Ȃ̂ł���B���{�Ɛ��E�́A���̍����̂悤�ɂȂ��Ă���̂��B�����Ă��ꂩ��A�ǂ����������ɐi��ł䂭�̂��B�������܂��ܐ����A���܂��܂Ȍ`�ő��݂̊W��z���Ă������̎Љ�̍s�������A�ł��邾���������͂������B
���j�̖T�ώҁA�ώ@�҂ł��肽���Ɗ肤����ŁA�s�����ƕs�����܂���ʂ�A���̎Љ���A���������ƏZ�݂悢�Љ�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂��B�s�K�Ȑl����l�ł����炷���@�͂Ȃ��̂��B���������グ�Ă����A�R����`���Ƃւ̌X���A�Ȃ�Ƃ��j�~������@�͂Ȃ��̂��낤���B
�ł����̑O�ɂ���ׂ����Ƃ�����B����͍��̓��{�ۂ��E���ɑ傫���X���Ă���Ƃ����������w�E���A�����̍����ɂ��̊�@�I�ȏ�[�����ĖႤ���Ƃ��B�ł�����́A���}�Ȉ�s���ɂƂ��āA���Ȃ荜�̐܂��d���ł���B�����ȕs���͂����Ă��A�قڌ���ɖ������āA�傫�ȕω����D�܂Ȃ��B���������ێ�I�ȉ��l�ςƌX���́A�����̑命���������Ă���X��������ł���B����Ȑl�B�ɁA�N���ʂ�ܓ�����o�āA�₽�����ɓ�����Ȃǂƌ����邾�낤���B
�ł͂ނ��뎩������A�ʂ�ܓ�����o�����Ǝv���Ă��炤���߂ɂ́A�ǂ�����Ηǂ��̂��B����́A���������̂܂܂ɓ`���A�����B���ǂ�ȏɒu����Ă��邩�A�������u����ǂ��Ȃ邩���A�������Ă��炤���Ƃ����Ȃ��̂ł���B�A�����̎��́A�f�}��t�F�C�N���������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Ȃ�ׂ��F�t���̖������łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ł����ꂪ���Ȃ����̂ł���B
�Ȃ��Ȃ�Љ����̑I���̒i�K�ŁA�ҏW�҂̉��l�ς��傫���e�����邩�炾�B����͏��̑I�������ƁA�����`���邱�ƂŁA�D�܂����炴��l���́A�l�I�Ȑ�`�i�v���p�K���_�j�̕Ж_��S�����ƂɂȂ�ꍇ�����邩�炾�B
�����ԂŋN���Ă��邱�ƁA���̖{���̎p�𑨂��邱�Ƃ��{���̎g���ł���͂��́A���̃��f�B�A��R�����e�[�^�[�́A���{�⊯���⍑�ɜu�x���A�����������ɂ������Ă���B��ؕ��Ȃ��ꍇ��������B�ŋ߃f���̕��F���ɋ߂��̂͂��̗Ⴞ�B���Ƃ����āA�S�V�b�v�n�̃��f�B�A�͐M�����Ɍ�����B�ł͂ǂ�����ΐ^��������̂܂܂ɔc���ł���̂��B
���ǁA�����̏���A�����͂��̒f�Ђ��W�߁A�������Ȃ����킹�Đ^����T��o���A�������͐��肷�邵�����@�͂Ȃ��̂ł���B
�������ł̕����̏��̔�r�i���̔�r�j�Ƌ��ɁA�����o�����i�܂��͎����j�̌o�܁A�������ԓI�ω���c�����i�c�̔�r�j�A�_���̐������͂���B�ߋ��̏��ƁA���݂̏����Ȃ��ŁA���݂̈��ʊW�������������B���݂́u�R�v�́A�ߋ��̎����Ɩ������邵�A���݂��m�肷��A���x�͉ߋ��̏����C�����Ȃ���ΐ����������Ȃ��Ȃ�B�����Ƃ̉R�͂����Ă�����ł���B�ߋ��̔������{���ŁA���݂̌������͌�����ɉ߂��Ȃ��B
���̉��̔�r�ƁA�c�̔�r�B���ꂾ�����A�����Ȃ���m�����l���������Ȃ��ꏎ���ɂł���A�B��̐^���ւ̐ڋߕ��@�Ȃ̂ł���B�ł�����͈ꌩ�e�ՂȂ悤�ł��āA���͒N�ɂł��o���鎖�ł͂Ȃ��̂�������Ȃ��B
�����̃��f�B�A��������N�W���鎞�ɂ́A�e���f�B�A���L�̉��l�ς�X����m���Ă����K�v������B�Œ�ł��A���x�������A�����ێ炩�A���ێ炩�̗����͕K�v���B
���Ԏ��ł̏���r���L�����ǂ����́A�ǂꂾ�������o���i�����j��ςݏd�˂��邩�ǂ����Ō��܂�B���̓_������wtw�͒N�ɂ����������Ȃ��Ǝv���B�M�l�X�͖����ł��A�u���K���A�Ƃm�x�̒��ݎ�����܂߂āA40�N�ȏ�́A�ꎞ�I�ɒf���͂����Ă��A��{�A�����̐ςݏd�˂�����A������`4�ň������A�����炭���e�̍�����10�����邾�낤�B
�Ƃ�ʼn^�c���Ă���T�C�g�Ȃ̂ŁA����������Ȃ��B������l�̉��l�ς��F�Z�����f���邱�Ƃ͔������Ȃ��B�A����������Ǝ�邩�A�Ό��Ǝ�邩�͓ǂސl���悾�B���̂����ŁA�ǂ��܂�wtw���ǎ҂Ƃ̊ԂŁA����̗��������L�ł��邩�A�W�]����������̂��B����͏����łȂ���Ε�����Ȃ��B
���ߐ肪�����ł͂Ȃ��A�x�ڂ��Ă�������������ł��Ȃ��B�ǓƂŕ��ȘV�l�ɂ��A���̏N�W�Ɣz�M�A��T��̔�r���͂Ǝv�l�������A�ʂĂ��Ȃ������Ă䂭�Bwtw����V�l�̎�I�ȓƔ��ŏI���\���͋ɂ߂č����B����ł����Ȃ����͂܂����ƐM���邵���Ȃ��̂ł���B
�T�Ԓ����i5.19�j�������̍߂Ɣ��A�É�Ζ�
�u�Ē��̔F������v�A���{�Љ�̕ϖe�v����
�c���������͎��̍l�������A10�N�O�ɂ͓��{�̗̓y�O�ɂ����p�ŋN�������͕����ɓ��{���Q�킷�邱�Ƃ͌��@�㋖����Ȃ������B���ꂪ���{�����̉��߉����ɂ��W�c�I���p���s�g�e�F�ŎQ�킪�\�ɂȂ����Ƃ�����ω����N�����B�����O��ɂ���ƁA��p�L�������{�L���Ƃ��h�q��{����G��n�U���\�͂Ȃǂ̋c�_�����Â鎮�ɍm�肳��铹���J�����B
10�N�O�̈�ʂ̓��{�����ɂ͂��������c�_���������]�n�͂Ȃ��A�����Ƃ����_�𐺍��ɏq�ׂ邱�Ƃ͍T�����B����������Ƃǂ��납��ʐl���E�������ƂƓ������Ƃ������n�߂Ă���B�����Ȃ�ƁA�u�G���U�߂Ă��邼�I�v�u���̂܂܂ł͂���Ă��܂��I�v�u�� ��A��ɂ�邵���Ȃ��v�Ǝ����}�������ɏ����n�߂����A�ȑO�Ȃ�u�푈�Ȃ�ĂƂ�ł��Ȃ��I�v�Ƃ������ΐ��_�����܂�\���������������A���́A�u�������A�������I �撣��A���p�I�v�̑升���ɂȂ鋰�ꂷ�炠��B �푈���~�߂�Ō�̍Ԃł��鍑�����_���S�����~�߂ɂȂ�Ȃ������܂����̂��B
�����炱���A�Ē��̊O���̒���Ƃ��A���{���_ �́u���ρv�����ɔF�������B�����A�̐S�̓��{�����͂���ɋC�t���Ă��Ȃ��悤���B�����J��ƂȂ��Ă���ł͒x���B���{�����́A�Ē��̎w�E���@�ɁA����́u�ϐ߁v�𑁂����߂�ׂ����B
�R�����g�F���͂╽�a���@�͓��{�ɂ͂��������Ȃ��B�ɐ^�삾�B
���������T�̂킾���܂�A���c���S
�u�O�Q��I��U��Ԃ�v����
�c����A��}����������������Ǝ����ł��Ȃ������悪����B���̂��������}���������B���5��ł͑O�C�̎����}�c�����u�����ƃJ�l�v�̊Ԉ��Ŏ��߂��Ƃ����̂� �����}����o���p���A���t�B�������������B��}�͌��҂���{���ł��Ȃ������B�啪�ł͂킸��341�[���ŁA�����}�V�l�̔��∟�I����������}�O�E�̋g�c���q��j���Ă���B�����ł��A�p���p���ł����ĂȂ������B����͖�}��1�}�̗�������}�̐ӔC���傫�����A����\�͑�\�����C����l���͂Ȃ��Ɩ������Ă���B
����������Ƃ������Ȃ��A�Ƃ��A���������������Ă���Ώ��Ă��̂ɂȂ��A�Ƃ������U��Ԃ�ł́A�H�p���Ƀp�^�[��h��Ȃ��璩���߂Ă��鎩���ƕς��Ȃ��B�����ő����ɐi�ނ����ɂȂ�Ȃ��悤�Ȑ��ʂ邳�����̌��ʂ��������̂ł͂Ȃ����B
�����@�̉��ߕύX���߂��鑍���Ȃ̓����������́A��������}�����m�V�c���̕����̒���n�܂����B���̌�A���g�̌��������ꂽ���̂́A�����̖�莩�̑̂������ĂȂ��Ȃ����킯�ł͂Ȃ��B���ق��R���R���ς�鍂�s���c��b���͂��߂Ƃ��āA�ӔC��Njy��������K�v���������B���̕ӂ�̃n���h�����O���}�Ƃ��Ă��܂�ɂ����肭���ł͂Ȃ��������B
���Ƃ��A�ݓc�����́A���q����̃��j���[�����������ׂĂ����Ȃ���A��̓I�ȍ����ɂ��Ă͑I����ɋc�_����Ƃ����Ƒ��ȋZ���g�����B������Ƒ��ł��u�F�X����Ă���Ă���݂����v�Ƃ������͋C�����������B��������}�ɂ͋�̓I�ɒNjy�ł����肪�������]�����Ă����͂��B��q�̑����Ȃ̓��������A�����ꋳ��Ǝ����}�̊W�A���{�w�p��c�̔C�����ۖ��A���s���ɔ]��ޖh�q��A��̉������Ȃ�LGBT���i�@�ȂǁA��莋���ׂ����ۂ��ςݏオ���Ă���B�������������w�E���A���Ԃ𖡕��ɂł��Ȃ������̂͂Ȃ��Ȃ̂��B���̖₢���̂���\�����g�ɓ��������悤�Ƃ��Ȃ��̂Ȃ�A�����Ɏ�����ׂ����낤�B
�R�����g�F���̒ʂ�B��������͋ʖ��������B��������͐������B�����͈��{���i�����Ɂj�������B
�֘A�L���F�_�ސ쌧�c��A������3��h�ɕ��h�B
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6462743
2329.��{����̎莆�@5/11
�G�����E��6������ǂ�ł�肫��Ȃ��C�����ɂȂ�܂����BSNS�֘A�̓��W�L����ʓǂ������߂ł��B���l�ԎЉ�ōł��_�[�N�ȕ������r�p�����l�b�g�Љ�ł��B��掁A�����͂��납�A���ʁA�w�C�g�A���ł�����̖��@�n�сB���ꂪ�l�b�g�Љ�ł��B�������q�����L�◧�Ԃ̂悤�ɁA�l�b�g���[�U�[���x���A�l�Ԃ̃l�K�e�B�u�ȕ����ɓ��荞��ŁA������悷��҂������ꂽ�B
���ɍ��A���E�Ő_�ƈ����A�P�ƈ��Ƃ̐킢�������Ɏn�܂��Ă���Ƃ���A�������߃l�b�g�́A���������l�Ԃ̗ǐS���ނ��݁A�l�Ԑ����������̂ɂ��邽�߂́A���D�̃c�[���ł��傤�B���_�̍r��Ɖ������l�b�g�Љ�ɁA�ǂ����ΐ��`�Ɛl�Ԑ������߂���̂��B�ǓƂȘV�K���}���́A�����ڂ̂Ȃ��킢�̓��X�͑����B
�Ƃ���Ŋݓc����A�������������ē����b�͎~�߂ɂ��܂��傤�B���̑O�ɂ��邱�Ƃ�����ł��傤�B���̂܂܂ł́A���Ȃ��͓��{�̌����j��ŁA���{�������A�ň��̎Ƃ��ė��j�ɖ����c�����ƂɂȂ�̂ł���B
����̑O�����̓T���f�[�����ƎG�����E����ł��B
�T���f�[�����i5.21�j�T���f�[���]�@�����O
�u���܂݂̓��ǖ@�����āA��ƂȂ������g��z������v����
�c���������s�@�؍ݎ҂ݏo���Ă����͓̂��̏o�����ݗ��Ǘ��̐��x�Ǝ����o���̌��ׂł���A �������҂̎����������߂邱�Ƃ� ����Еt����̂͋��}���B�D�悷�ׂ��͂����܂ŕs�@�؍ݏ�Ԃ̉����ł���A���e���Ԃ̒Z�k�ł���A���̂��߂̖@�����ł���B���Ƃ��Ύ��e�ɍۂ��Ďi�@�����̓K�ۂf���鐧�x�̓����͕K�{�����A��F��͕s�F��ł��A�l���I���n����̕⊮�I�ی�Ώێ҂ւ̔F���A�ݗ����ʋ��̐v���ȉ^�p�Ȃǂ̉~���Ȏ����̐��s�́A���e��肸���Əd�v���낤�B
�����A�����ދ��������o�Ă��A�������ށu���Ҋ����ҁv�́A��N���̎��_��4233�l�B�����ɂ͓��{�Ő��܂�����18�Ζ����̎q�ǂ�201�l���܂܂��B�e�̎�����ł���A���{�ꂵ���b�����A���ɓ��{�̊w�Z�ɒʂ��Ă���q�ǂ����A�e�ƂƂ��ɋ������҂��邱�Ƃɂ͂ǂ�ȍ��������Ȃ��B�ނ���A�e���q���ݗ����i�̊g�[�ŕs�@�؍݂̏�Ԃ��������A���{�Ő����̊�Ղ�z����悤�Ɏ����Ă䂭�ق����A�͂邩�ɎЉ�̈���Ɏ�����Ƃ������̂ł���B
���������{�l�ɂƂ��āA����͂������đ��l���ł͂Ȃ��B���ɕ�����1�����̎��̂ł́A�ւ�������Ɗ֓����܂ޓ����{�S�̂��l�̏Z�߂Ȃ��m�n�ɂȂ��Ă����ƌ�����B���ɗ����C�g���t��n�k�⌴���̏d�厖�̂ŁA���{�l���C��n���ē����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ɂȂ����Ƃ��A�������͂܂��ɓ�ɂȂ�̂����A�\���ɐl���ɔz���������������邾�낤���B���܂��܂Ȕ��Q���璅�̂ݒ��̂܂ܓ���Ă���4233�l�̌���ɂ������ɂ߂Ȃ����{�l�́A���g����ƂȂ����Ƃ��̂��Ƃ�z�����Ă݂�ׂ��ł���B
�R�����g�F���{�l�S���ɓǂ�ŗ~�����B
�������q���Y�̐����_
�u�̎��R�x�����L���O71�ʂ̓��{�����疳���[��������v����
���쌧�y���G7�O����b��̗l�q����ނȂǂŁA�����ɒ��߂̑؍݂������A�����B
���쌧���͂܂��߂Ŗ����`��厖�ɂ���Ǝv������ł����̂����c�B���\�n���I�̌㔼��A���̒������I�ŎO�������[�B�l�̑��͗����҂��萔��1�����A�萔����ɂȂ����B
���ꂼ��A����͂���Ƃ͎v������ǁE�c�B�����A���E �����ނ��Ȃ�����A�V�l�ɏ����ڂ��Ȃ��̂��낤�B�ŁA�����[���I�ɂȂ�B
�����v���ē����ɋA��A�V����ǂނƁA�֓�5���̌��u��c���I����173�I����̂���56�I�����88�l�������ݓ��I�B�� 460���l�̗L���҂��� �[�ł��Ȃ������B�s�s���ł������[���������Ă���̂��B�����̂ǐ^�u������v�̋撷�܂Ŗ����[���I�������B
������������Ǔ��{���ɍs���Ȃ��I��������邪�A�l�X���u���[�v�Ƃ����V�X�e����Y��Ă��܂��B�u�����`�̕���v�ł͂Ȃ��̂��H
�����g�������u�����Ȃ��ƍفv���i�s����B���낵���Ȃ����B
�u�����[�v�������錴���͇@�������Ȃǂł̐l�������A�c����V�Ȃǂ̒Ⴓ�B�抄��Ȃǂ̑I�����x �\�Ȃǂƌ����Ă��邪�A�����Ŗ�}�����㉻�v���A�^�}�����N��߂�c�Ȃ�D���قǂ̐������Ȃ��̂�������Ȃ��B
�������u�����[�v�̍ő�̌����́u���f�B�A�̓�����̕v�ɂ���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�V�Ԃ��A�e���s���A�G�����u�n�������v�ɖ��S�B�قƂ�ǂ̏�����̂́u���\���́v����B�L�҃N���v�i�ɉ������郁�f�B�A�j������Ɛ肵�āA�L�҂͂܂�œw�͂��Ȃ��悤�Ɍ�����B�n���Ȋ֍���u�Ռ��I�ȃX�N�[�v�v�̂悤�ȋL���͂قƂ�ǂȂ�����A�Z ���́u�n��v�ɖ��S�ɂȂ�B
���N���\�����u�����Ȃ��L�Ғc�v�ɂ��u���E�̎��R�x�����L���O�v�ŁA���{��180�J������71�ʁB���ʂɕ]������闝�R�͊�����邪�u�L�҃N���v�v�Ƃ������͊��̒��ǂ��O���[�v�̑��݂��ᔻ����Ă���i���Ȃ݂ɁA�A�W�A�ł͑�p��38�ʁA�؍���43�ʁj�B
�Ƃ��������f�B�A���u�n����́v�ɗ͂����Ȃ��ƁA�u�����[�v�͂����Ƒ����邾�낤�B
�u�����[�v������邽�߂ɂ́u�c���萔�v��啝�Ɍ��炷�����Ȃ����낤�B
�����Ƃ��A�������鍑��c���̐��i���{��717�l�Ő��E6�ʁA���Ȃ݂ɕč���535�l��24�ʁA�؍���300�l��45�ʁj�����炷�L�b�J�P�ɂȂ�Ƃ悢���i�j�B
�R�����g�F�c���萔�팸�A�傢�Ɏ^���ł��B
�G�����E6�����A�_�{�O���𖢗��i����邽�߂Ɂ@�X�{�q�V
�u��{���ꂳ�Ŋ��ɓ`�������Ɓv����
�\��{���ꂳ��̎莆�i�S���j�\
�����s�s�m��
���r�S���q�l
�ˑR�̂��莆�A���炵�܂��B
���͉��y�Ƃ̍�{����ł��B
�_�{�O���̍ĊJ���ɂ��Ď��̍l�������`�������M���Ƃ�܂����B
�ǂ�������ǂ��������D
�����Ɍ����āA�ڂ̑O�̌o�ϓI���v�̂��߂ɐ�l��100�N�������Ď���ĂĂ����M�d�Ȑ_�{�̎��X���]���ɂ��ׂ��ł͂���܂���B
�����̎��X�͂ǂ�Ȑl�ɂ����b�������炵�܂����A�J���ɂ���ĉ��b��͈̂ꈬ��̕x�T�w�ɂ����߂��܂���B���̎��X�͈�x���������x�Ǝ��߂����Ƃ��ł��Ȃ����R�ł��B
�����Z�ރj���[���[�N�ł́A2007�N�A�����̃v���[���o�[�O�s�����s����100���{�̖�A����Ƃ����u���W�F�N�g���X�^�[�g�����܂����B���ʂ�S�̌��N�ւ̔z���A�Љ�`�A�����ĉ���薢���̂��߂ł���Ƃ̖ڕW���������Ă̂��ƁA�d��ł��BNY�s�ɒǐ������ ���ɁA�{�X�g����LA�Ȃǂ̃A�����J�̑�s�s�⒆�K�͓s�s�ł��A�уL�����y�[�����i��ł��܂��B�ڂ����͂�����̋L�������Q�Ƃ��������G
https://globe.asahi.com/article/14629731
���ܐ��E��SDGs�𐄐i���Ă��܂����A�_�{�O���̊J���͂ƂĂ������\�Ȃ��̂Ƃ͌����܂���D�����\�ł����Ƃ���Ȃ�A�����̎��X�������������Ă̎q���B�ւƎ�n����悤�A���ݐi�߂��Ă���_�{�O���n��ĊJ���v��𒆒f���A�v����������ׂ��ł��B
�������u�s�s�Ǝ��R�̐��n�v�ƈʒu�Â��A���̃S�[���Ɍ��������哱�����邱�Ƃ����A���E�̏̎^��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����āA�_�{�O���𖢗��i����邽�߂ɂ��A�ނ��낱�̋@��ɐ_�{�O�������{�̖����Ƃ��Ďw�肵�Ă����������Ƃ��ނ�ł��肢�����������܂��B
���Ȃ��̃��[�_�[�V�b�u�Ɋ��҂��܂��B
�ߘa5�N2��24��
��{����
���莆�́A���r���̂ق��A�i�������Ȋw���A�s�q�����������A�g�Z�V�h�撷�A����`�撷�ɗX�������B������3��2���B
�֘A�L���F�a�������t��U��Ԃ�B�����V���B
https://www.tokyo-np.co.jp/article/243643
�E���{�̃��f�B�A�̔F�m�x�B
https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20230510-00347977
�E���U���ߐ����̓����ɒ�؊��B
https://www.tokyo-np.co.jp/article/248946
�R�����g�F���ȏȂ��J��Ԃ�������v������ȂǁA�ŏ����瓮�����������������B�דc���A�����c���A�������������܂��̂܂܁B����œ��ꋳ����𐁂��Ԃ�����ڂ����Ă��Ȃ��B����ł݈͊ꑰ�̖S��̎v�����܂܂��B�������ǂ̃��f�B�A���A���̘b������グ�悤�Ƃ��Ȃ��̂́A�W���[�i���Y���Ƃ��Ĉ����̋ɂ݂��B�B
�E�������̓��{�́A���f�Ɛ����̉�������B
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ba61d1ad94890879ea664579073ed92f365dd37
�R�����g�F�ł͗ߘa�̍��́B
�EAI�̊댯���Ɍx���B
https://www.jiji.com/jc/article?k=20230509044438a&g=afp
2330.���ɓ����@5/11
�G�����E��6������ǂ�ł�肫��Ȃ��C�����ɂȂ�܂����BSNS�֘A�̓��W�L����ʓǂ������߂ł��B���l�ԎЉ�ōł��_�[�N�ȕ������r�p�����l�b�g�Љ�ł��B��掁A�����͂��납�A���ʁA�w�C�g�A���ł�����̖��@�n�сB���ꂪ�l�b�g�Љ�ł��B�������q�����L�◧�Ԃ̂悤�ɁA�l�b�g���[�U�[���x���A�l�Ԃ̃l�K�e�B�u�ȕ����ɓ��荞��ŁA������悷��҂������ꂽ�B
���ɍ��A���E�Ő_�ƈ����A�P�ƈ��Ƃ̐킢�������Ɏn�܂��Ă���Ƃ���A�������߃l�b�g�́A���������l�Ԃ̗ǐS���ނ��݁A�l�Ԑ����������̂ɂ��邽�߂́A���D�̃c�[���ł��傤�B���_�̍r��Ɖ������l�b�g�Љ�ɁA�ǂ����ΐ��`�Ɛl�Ԑ������߂���̂��B�ǓƂȘV�K���}���́A�����ڂ̂Ȃ��킢�̓��X�͑����B
�Ƃ���Ŋݓc����A�������������ē����b�͎~�߂ɂ��܂��傤�B���̑O�ɂ��邱�Ƃ�����ł��傤�B���̂܂܂ł́A���Ȃ��͓��{�̌����j��ŁA���{�������A�ň��̎Ƃ��ė��j�ɖ����c�����ƂɂȂ�̂ł���B
����̑O�����͒����V���i5.12�j��1�y�[�W�ځA�Ж��̉��́A�܁X�̌��t�A�h�c����ł��B
�������͂������Ƃ���������ۂ����Ȃ��B�����O
�����́A���Ԃ̗��݂ɒ��ݍ��ނ��肾�����p�Ɋׂ邪�A�����ɛs�܂ꂽ�u������q�v�𐫋}�ɛz�������悤�Ƃ���ƁA�b�`�̂��̂��肪����Ă͂����ɕY�������A����ȋt���������p�ɂ͂܂�ƁA��ȉƂ͕����̍���J���B���݂͖����Ɍ����Ȃ�����u���݁v�ɐ[���r���~�낵�Ă䂭�̂��|�p�̖������ƁB�����l�ފw�ҁE��c�����Ƃ̉������ȁw���E���ƂE�l�ԁx����B
�R�����g�F���̃l�b�g�����i����Ȃ��̂�����ł����j�A�������̓l�b�g�̒����B���܂��ɋt�����̑ޔp�ł��傤�B
�����̎��ԂɁA�u���i�������j�ɓ��i�݂��j�i���j���Η[�i�䂤�j�ׂɎ��i���j���Ƃ��i���j�Ȃ�v�Ƃ������t���w�т܂����B���̐��̓����𗝉��ł���A�����v���c�����Ƃ͂Ȃ��A���ꂭ�炢�l�̓������߂邱�Ƃ͓���A�Ƃ����悤�Ȏ�|�������悤�Ɏv���܂��B�����҂̋����ł��傤���A�������������҂̒��ԓ�������Ďv�����Ƃ́A���Ȃ�A�i�ȑO�͏o���Ȃ������j�����͂܂��Ȕ��f���s�����o���������Ƃ������o�ł��B���_�A����͎Љ�I�n�ʂ̌���i�����j�⎑�Y�`���i���j�̘b�ł͂���܂���B�l�ԓI�Ȑ����ƁA���_�i�����Ɗ���j�̘B���̘b�ł��B���ł���A�̂̂悤�Ȗ��n�Ȕ��f�ł�������A�����͖��f���|����悤�Ȃ��Ƃ����Ȃ����낤�Ƃ����o���m�ł��B�����炱�ꂩ�炪�{���̐l���Ȃ̂ł��B�Ƃ��낪������c�莞�Ԃ����Ȃ��B�������I���̃z�C�b�X�������Ă����������Ȃ��Ƃ���܂ŗ��Ă��܂��Ă��܂��B�u���O����������v�ƌ�����ΕԂ����t�͂���܂���B�ǎ҂̏��Z���o�́A���ɂ����g�́u���v���ɂ߂Ă�����ł��傤���B
����ɂ��Ă��A���Ƃł́A�����Ɗ����̎��Ԃ𑝂₷�ׂ����Ǝv���܂��B���̊ܒ~�̐[���͐��m�����̉����y�ԂƂ���ł͂���܂���B�ݓc�₠�������́i�h�p������������ǁj�S���킩�����Ⴂ�Ȃ��悤�����A�����ɂ�4��N�̒m�b������̂ł��B
�E�ݓc�B�^�C���̋L���̒��g�ƌ��o�����A���܂�ɈႤ�B
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6463104
�R�����g�F�W�F�X�`���[�������낤���A�ے肵�Ȃ����͂܂������B
�E75�Έȏ�A��Õی��������グ�B
https://news.yahoo.co.jp/articles/484fba09116685c9b777f5e6c058ba08b74fbd59
�R�����g�F��k����Ȃ��A�������略���Ă���Ǝv���Ă���̂��B
��Ј��Ȃǂ̑�2����ی��҂ŔN��300���~�̏ꍇ�A�N�ԕی����́A�����N���ی���19��9080�~�{26��3520�~��46��2600�~�B
�������N��300���Ƃ͌��N�ŕ����I�Ȑ����ǂ��납�A�����Ă䂭�̂ɂ��肬��̎������B�����畽�ϓI�Ȑ��тł͍������S���ۂ�����B�����ɒlj��̕��S��������O�ɁA���z�̕����č��̌����l�Ŕ���Ȃ���������낤�B�ǂ����Ă����킪�~������A�x�T�w�ɗ���Ŕ����ĖႦ�Ηǂ��B
�E��t�n�k�A��s�����Ƃ̊֘A�́B
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6462987
�E��t�n�k�A��s����6200��̃G���x�[�^�[��~�B�s�s���̕|���B
https://news.yahoo.co.jp/articles/007254aae5c0c8582499d617d43b48f5c303ed6c
�E�\�o�n�k�A�k�����k�ֈړ��B
https://news.yahoo.co.jp/articles/82514331375ebe261f867e940dc1330732d6c430
�֘A�L���F�����������܂�Ƃ͍l���ɂ����B
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230512/k10014065531000.html
�E���R���ǎ����A���A�g�D��莩���B����B�������䂪�w�E�B
https://news.yahoo.co.jp/byline/shivarei/20230512-00349177
�R�����g�F�Ƃ���łȂ��ŋ�NHK�͍���p�����Ȃ��̂��B
�E���r�S���q�A��������߁B
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230512-OYT1T50215/
�R�����g�F���R�͔�J�Ȃǂł͂Ȃ��B�O���J���ւ̊O�����f�B�A�i�ƍ�{����j�̔ᔻ���낤�B���a�����������ɁB
�E�ˑ��Ǐ����J�W�m�̈ŁB
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20230511-OYO1T50023/
����̑O�����̓T���f�[�����ƎG�����E����ł��B
/